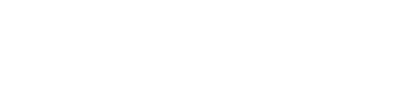脳出血を含む脳卒中は、命を脅かす病気として知られていますが、一命を取り留めた場合でも後遺症に悩むことが多い病気です。
脳出血の後遺症は、手足のしびれや言語障害など多岐にわたり、正確に知る人はあまり多くありません。
この記事では、脳出血の主な後遺症を一覧でご紹介していきます。
脳出血で後遺症が残ったときに家族ができることや、障害年金についてもお伝えしていきますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
目次
脳出血の後遺症一覧
脳出血の主な後遺症を一覧でご紹介します。
- 片麻痺(半身麻痺)
- 言語障害(失語症・構音障害)
- 高次脳機能障害
- 視力・視野障害
- 嚥下障害
- 感情のコントロールの変化
- 中枢性疼痛(痛み・しびれ)
それぞれ見ていきましょう。
脳出血の後遺症(1)片麻痺(半身麻痺)
脳出血の後遺症として多く見られるのが、体の左右どちらかの動きが悪くなる片麻痺(半身麻痺)です。
脳出血によって脳の運動神経が損傷を受けると、その支配下にある手足や顔面などに麻痺が生じます。
片麻痺の主な症状を下表にまとめます。
| 種類 | 症状など |
|---|---|
| 運動麻痺 | ・手足や顔の筋肉が動きづらくなる・歩行困難や物を持つ動作が制限される |
| 感覚障害 | ・麻痺した側で触覚や温度感覚が鈍くなる・感覚がなくなる |
| 筋肉が固まる | ・時間の経過とともに筋肉が固まったり、つっぱる感じがする |
脳出血後の早期から適切なリハビリを行うことで、麻痺の改善や残された機能を最大限に活かすことが期待できます。
脳出血の後遺症(2)言語障害(失語症・構音障害)
脳出血の後遺症の一つに、言葉によるコミュニケーションが困難になる言語障害があります。
脳出血によって言語機能を司る脳の領域が損傷を受けることで、主に「失語症」と「構音障害」という二つの異なる症状が現れることがあります。
どちらも脳出血後の生活において、他者との意思疎通に大きな影響を与える後遺症です。
失語症と構音障害の特徴や症状を下表にまとめました。
| 種類 | 特長 | 症状など |
|---|---|---|
| 失語症 | 言語中枢が損傷されることで、言葉を話す、理解する、読む、書く能力に障害が生じる | ・聞いたことを理解するのが難しい ・言葉が出てこない ・間違った言葉を話す ・読み書き能力の低下 |
| 構音障害 | 舌、唇、喉などの運動機能が低下し、発声や発音が不明瞭になる | ・ろれつが回らない ・声がかすれる ・話の途中で息切れする ・声量が小さくなる |
言語障害は脳出血後に頻繁に見られる障害ですが、早期からの言語療法などのリハビリテーションによって、症状の改善やコミュニケーション能力の向上が期待できます。
脳出血の後遺症(3)高次脳機能障害
脳出血の後遺症の一つである高次脳機能障害は、記憶力や集中力、判断力といった、人が社会生活を送る上で重要な認知機能に障害が生じる状態を指します。
脳出血によって脳のさまざまな領域が損傷を受けることで、これらの機能がうまく働かなくなることがあります。
高次脳機能障害の主な症状を下表にまとめました。
| 種類 | 症状など |
|---|---|
| 記憶障害 | ・新しい情報を覚えられない ・過去の出来事を思い出せない |
| 注意障害 | ・集中力の持続が困難 ・複数の作業を同時に処理できなくなる |
| 遂行機能障害 | ・計画立案や問題解決が難しくなる ・段取りが必要な作業に支障が出る |
| 社会的行動障害 | ・感情のコントロールが困難になる ・突然泣く、怒るなど衝動的な行動をとる |
高次脳機能障害は、外見からは分かりにくいため、「目に見えない後遺症」とも言われています。
脳出血による後遺症である高次脳機能障害の現れ方は、人によってさまざまであり、単一の症状だけでなく、複数の症状が複合的に現れることもあります。
リハビリテーションを通じて、失われた機能の一部の回復を目指したり、残された機能を活用する方法を習得したりすることが重要だといえるでしょう。
脳出血の後遺症(4)視力・視野障害
脳出血の後遺症として、視力や見える範囲に影響が出る視力・視野障害が現れることがあります。
脳の視覚情報を処理する領域が脳出血によって損傷を受けると、さまざまな見え方の異常が生じ、日常生活に支障をきたすことがあります。
視力・視野障害の主な症状を下表にまとめました。
| 症状や見え方 | 日常生活への影響 |
|---|---|
| 左右どちらかの視野が半分見えなくなる | ・歩行時の衝突 ・読書の際の読み飛ばしなど |
| 物が二つに見える | ・距離感の把握困難 ・階段の上り下りの際のふらつき ・細かい作業の困難さなど |
| 視野の一部が黒く抜け落ちたり、ぼやけて見えなくなったりする | ・見えない部分の物の認識遅れ ・運転時の危険察知の遅れなど |
視力・視野障害は、リハビリテーションによって改善が見込まれる場合もあります。
眼科医や視能訓練士といった専門家の指導のもと、適切な訓練や補助具の活用を行うことが大切です。
参考:くまもと県脳卒中ノート|熊本県脳卒中・心臓病等総合支援センター
脳出血の後遺症(5)嚥下障害
脳出血の後遺症の一つである嚥下障害は、食べ物や飲み物をスムーズに飲み込むことが困難になる状態です。
脳出血によって、嚥下に関わる神経や筋肉が損傷を受けることで発生します。
脳出血後の後遺症としての嚥下障害は、食事の際の安全性を大きく損なうだけでなく、全身の健康状態にも影響を及ぼす可能性があります。
嚥下障害の主な症状は次のとおりです。
- 飲み込みに時間がかかる
- 食事の中によくむせる
- 誤嚥(食べ物や飲み物が気管に入る)による肺炎のリスク
- 栄養不良や脱水症状につながる可能性がある
誤嚥を繰り返すと、肺炎を引き起こすリスクが高まります。
また、スムーズに食事が摂れないことで、栄養不良や脱水症状につながることもあります。
言語聴覚士などの専門家による嚥下訓練や、食事の形態や姿勢の工夫などを行うことで、安全に食事を摂るための改善が期待できます。
参考:くまもと県脳卒中ノート|熊本県脳卒中・心臓病等総合支援センター
脳出血の後遺症(6)感情のコントロールの変化
脳出血の後遺症として、感情のコントロールが以前と比べて難しくなることがあります。
脳出血によって、感情の動きを調整する脳の部位、特に前頭葉や側頭葉などが影響を受けることで、感情の抑制がうまくいかなくなるのです。
「脳出血後に急に人が変わったようになった」と感じることもあるようで、ご本人やご家族にとって理解しにくい後遺症かもしれません。
主な症状としては、次のようなことがあります。
| 種類 | 症状など |
|---|---|
| 情動失禁 | ・些細なことで急に泣いたり怒ったりする ・感情が抑えられなくなる |
| 感情の不安定さ | ・怒りっぽくなる ・悲しみやすくなる ・感情表現が乏しくなる |
| 衝動的な行動 | ・感情を抑える力が低下 ・突発的な怒りや衝動的な行動が増える |
ご家族は、これらの変化が脳出血による影響であることを理解し、温かく見守ることが大切です。
脳出血の後遺症(7)中枢性疼痛(痛み・しびれ)
脳出血の後遺症の一つに、慢性的な痛みやしびれが生じる中枢性疼痛があります。
脳出血によって痛みを伝える神経回路が損傷を受けることで、本来痛みとして感じないはずの刺激が痛みとして認識されるのです。
中枢性疼痛は、神経障害性疼痛の一種であり、治療が難しい慢性的な痛みとして知られています。
中枢性疼痛の主な症状には次のようなものがあります。
- 焼け付くような熱感
- まるで凍っているような感覚
- 針で刺されるような鋭い痛み
- 骨の奥深くから響くような、重く鈍い痛み など
特徴的なのは、軽い接触や温度変化といったわずかな刺激によって、激しい痛みが誘発されることがある点です。
痛みは持続的な場合もあれば、断続的に現れることもあり、日常生活に大きな支障をきたします。
痛みを完全に取り除くことが難しい場合もありますが、適切な治療と周囲のサポートによって、痛みの軽減や生活の質の改善を目指すことは可能です。
脳出血の後遺症が残るとどうなる?
脳出血の後遺症が残ると、日常生活の様々な場面でこれまで当たり前にできていたことが困難になり、生活に大きな変化が生じます。
まず、食事、入浴、着替え、移動などが一人でできず、介助が必要になる場面が増えることがあります。
また、仕事をしている方の場合、脳出血による後遺症の程度によっては、元の職場への復帰が難しくなることもあります。
さらに、これまで一人でできていたことができなくなることへのストレスや、周囲との違いを感じて孤独感を抱える方も少なくありません。
脳出血後の生活は、身体的なリハビリテーションだけでなく、精神的なサポートも非常に重要になります。
家族にできることは?支える側の心構え
脳出血の後遺症と向き合うご本人にとって、最も身近な存在である家族の支えは、回復への大きな力となります。
脳出血による後遺症からの回復を支えるために、ご家族ができること、そして支える側の心構えについてお伝えしていきます。
リハビリへの協力
リハビリへの積極的な協力は、ご家族にできる重要なサポートの一つです。
ご自身での移動が困難な場合や、安全面に不安がある場合には、ご家族がリハビリ施設への送迎をサポートすることが望ましいでしょう。
また、可能な範囲でリハビリに付き添うことも、ご本人の状況を理解し、医療従事者との連携を深める機会となります。
理学療法士や作業療法士などと直接話すことで、ご本人がどのような点に困っているのか、どのようなサポートが必要なのかを情報共有でき、より効果的なリハビリにつながる可能性があります。
さらに、リハビリは時に辛く、モチベーションの維持が難しい局面もあります。
そのようなとき、そばでご家族が励まし、支えることで、ご本人は前向きな気持ちを保ちやすくなります。
温かい言葉かけや、小さな目標達成を一緒に喜ぶことなどが、リハビリへの意欲を高める力となるでしょう。
生活環境の見直し
脳出血の後遺症が残った場合、ご本人が自宅で安全かつ快適に過ごせるように、生活環境を見直すことはとても大切です。
脳出血による後遺症の種類や程度によっては、これまで何気なく行っていた家の中の移動や日常生活動作が困難になることがあります。
ご家族全員で協力し、必要に応じて住環境を整えることを検討しましょう。
主な見直しポイントは次のようなことです。
| 見直しのポイント | 具体的な対策の例 |
|---|---|
| 段差の解消 | ・玄関や廊下の段差をスロープにする・床の段差をなくす |
| 手すりの設置 | ・廊下、トイレ、浴室などに手すりを設置する |
| 床材の変更 | ・滑りにくい材質の床材を選ぶ・滑り止めマットを敷く |
| 照明の改善 | ・明るい照明にする・足元灯を設置する |
| 家具の配置の見直し | ・通路を広く確保する・必要なものがすぐに手に取れるように配置する |
すぐに対応できないこともあるかもしれませんが、できるところから順番に改善していくといいでしょう。
心のケアが大切
脳出血の後遺症と向き合う中で、ご本人の心のケアはもちろんのこと、支えるご家族自身の心の健康もとても大切です。
ご本人が感情的になったり、落ち込んだりするときには、頭ごなしに否定せず、まずはその気持ちに寄り添い、理解しようと努めることが大切です。
「つらいね」「大変だったね」といった共感の言葉をかけ、安心できる雰囲気を作るように心がけましょう。
また、ときには「そっとしておく時間」も必要です。
過度な励ましや詮索は、かえってご本人を追い詰めてしまうこともあります。
一方、介護は長期にわたることが多いため、介護するご家族も無理をしすぎないように注意しましょう。
休息時間を確保したり、趣味の時間を持ったりするなど、心身のリフレッシュを意識することが大切です。
また、無理にすべてをご家族だけで抱え込まず、必要に応じて介護保険サービスやヘルパーの利用など、地域の福祉サービスを活用することも視野に入れましょう。
お互いを思いやり、気持ちよく過ごせるように工夫していくことが、脳出血後の生活を穏やかに送るための鍵となります。
脳出血の後遺症があると障害年金の対象になることも!
脳出血で後遺症が残ったときは、障害年金をもらえることがあります。
障害年金とは、現役世代の人が病気やけがで障害があり、生活や仕事に支障があるときに申請できる制度で、脳出血で後遺症が残った場合も申請対象です。
障害年金は、国民年金に加入している方が対象となる「障害基礎年金」と、厚生年金に加入している方が対象となる「障害厚生年金」の2種類があります。
どちらの年金が受給できるかは、脳出血で初めて医療機関を受診したときにどの年金制度に加入してたかで決まります。
障害年金の詳細は、下記の関連記事をご覧ください。
 障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
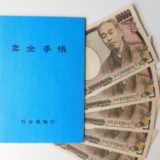 【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について
【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について
障害年金の申請は難しい?
障害年金の申請は、書類の準備や作成など手間のかかる作業が多く、「大変だ」と思われることが多いです。
障害年金の申請時には、自分の症状や生活での困り事などをまとめて書類を作成しますが、審査に必要な情報を的確に記載するのは、難しいという人が多くいます。
申請までに何度も年金事務所に通うなど、脳出血の後遺症がある人が自分で申請するにはハードルが高いでしょう。
ご自身や家族だけで障害年金の申請ができないと思ったら、社労士へ依頼することを考えてみることをおすすめします。
なお、脳出血での障害年金受給については、関連記事でわかりやすくご紹介しています。
 脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
脳出血での受給事例
脳出血で、ピオニー社会保険労務士事務所にご依頼いただき、受給できた事例をご紹介します。
脳出血で障害厚生年金1級を受給した事例
ご相談者:50代男性
傷病名:脳出血(右視床出血)
認定結果:障害厚生年金1級(障害認定日の特例)
年金額:約250万円
【ご相談時の状況】
右視床出血で左半身に麻痺が残り、初診日から6か月経った頃にご相談いただきました。
すでにリハビリは終了し、仕事に復帰しようとしている状態で、お話の内容から後遺症の症状が固定されているようでした。
【相談から申請までのサポート】
肢体の障害としては左上下肢をほとんど使うことができず、歩行困難であることから2級以上には該当すると判断しました。
初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めない症状固定と思われました。
そのため、「障害認定日の特例」を使ってすぐに障害年金の請求準備ができるとご説明いたしました。
現在の主治医に診断書作成を依頼したところ、既に左上下肢は症状固定と診断され、出来上がった診断書を見ると2級は確実で、1級に認定されてもおかしくない内容でした。
【審査の結果】
症状固定も認められ、初診日から6か月で肢体の障害1級を受給することができました。
脳血管疾患で症状固定と診断された場合には、初診日から1年6か月経過していなくても障害年金を請求することができるということを、知らない病院や医師が多いです。
ピオニー社会保険労務士事務所では、障害年金の特例などの制度も熟知しており、より早く受給できるように努めています。
このほかにも多くの脳梗塞・脳出血の受給事例がありますので、ぜひご覧ください。
まとめ
脳出血は命を脅かす怖い病気ですが、一命を取り留めた場合でも後遺症が残ることがあります。
半身麻痺や視力・視野障害など、後遺症の種類は多岐にわたりますが、生活や仕事に支障があるときには障害年金を申請できることがあります。
障害年金の申請は準備する書類が多く、何度も年金事務所に通うなど、自分や家族では申請が難しいことが多いです。
もしあなたや家族が、脳出血の後遺症で生活に困っているなら、障害年金を受け取れるかどうか、一度社労士に相談してみてください。
障害年金が受給できれば、今後の生活が大きく変わるかもしれません。