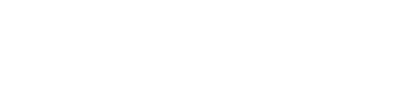「障害年金は働いている人はもらえない」
こんなことを耳にしたことはありませんか?
実は、障害年金は働いている人でも3つの受給条件を満たせば、受け取ることができます。
そこでこの記事では、障害年金は働きながらもらえるのか、受給のポイントを3つご紹介します。
仕事はしているけれど、障害の状態が辛いから障害年金を申請したい人やそのご家族が知りたい情報をぎゅっとまとめてお知らせするので、ぜひ参考にしてください。
目次
障害年金は働きながらもらえるの?
結論からお伝えすると、働きながら障害年金をもらうことはできます。
障害年金を申請できる3つの条件のなかに「働いていないこと」という条件はありません。
- 初診日要件…初診日に国民年金か厚生年金の被保険者であること
- 保険料納付要件…初診日の前日において一定期間保険料を納めていること
- 障害状態要件…原則として、障害認定日に国が定める障害等級にあてはまること
つまり、働いている人でも障害等級に該当する状態であれば、障害年金は受け取れます。
また、厚生労働省の統計では障害年金を受ける人の約半数が仕事を持ち、働いていることが公表されています。
【障害年金を受けている人(20歳~59歳)の就労状況】
| 障害の種類 | 就労率(%) |
|---|---|
| 身体障害 | 48.0 |
| 知的障害 | 58.6 |
| 精神障害 | 34.8 |
上記の表から、障害年金を働きながら受け取ることは決して珍しいケースではないことがわかるでしょう。
また、障害の中には就労の有無が審査に影響しないものもあるので、次章で具体的にご紹介します。
障害年金の3つの受給条件については関連記事でわかりやすくご紹介しています。
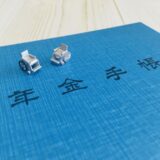 障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者
障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者
障害年金を働きながらもらえるケースとは?
働きながら障害年金を申請する場合、疾患により認められやすいものとして次の2つがあります。
- 就労の有無が審査に影響しない傷病
- 検査で障害の状態が測れる傷病
順番に見ていきましょう。
(1)就労の有無が審査に影響しない傷病
就労の有無が審査に影響しない傷病は、原則として障害等級が決まっているため、仕事をしていたとしても障害年金の審査に影響がありません。
就労の有無が審査に影響しない傷病の主な例を下表にまとめました。
【就労の有無が審査に影響しない傷病の主な例】
| 疾患・状態 | 障害等級 |
|---|---|
| 人工透析 | 2級 |
| 人工関節 | 3級 |
| 心臓移植、人工心臓の移植・装着 | 1級 |
| 人工弁、心臓ペースメーカー | 3級 |
| 人工肛門 | 3級 |
例えば、人工透析を受ける人の場合、定期的に透析する手間と時間が不可欠で、日常生活や仕事が大きく制約されることが明らかです。
同様に、人工関節を入れたり、人工肛門を装着した場合も、生活するうえで支障が出ることが客観的に明らかにわかる症例では、就労の有無が障害年金の審査に影響しません。
心臓移植や人工心臓等の術後は1級に認定されますが、1~2年程度経過観察した上で症状が安定しているときは、再認定で等級が変わることがあります。
(2)検査で障害の状態が測れる傷病
検査で障害の状態や程度が数値でわかる疾患についても、就労の有無が障害年金の審査にほとんど影響を与えません。
障害の程度が数値でわかる主な疾患を下表にまとめました。
【障害の程度が数値でわかる疾患の例】
| 傷病 | 症例 | 障害等級 |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下 | 1級 |
| 聴覚障害 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 | 1級 |
| 上肢の障害 | 両上肢の全ての指を欠くもの | 1級 |
| 下肢の障害 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 1級 |
例えば、交通事故などで足を切断するけがを負った人が、事務作業など車椅子でもできる仕事に就いた場合は、フルタイムで働いたとしても障害年金の審査に影響はありません。
うつ病やがんだと働きながら障害年金をもらえない?
検査で体の不自由さの度合いがはっきりと分からない病気(例えば、うつ病やがんなど)の場合、働きながら障害年金を受け取るのは難しいです。
なぜなら、「働けている」という状況から、「日常生活に著しい支障があるほど重い症状ではない」と判断されてしまう傾向があるからです。
しかし、決して「働いている=絶対に障害年金はもらえない」というわけではありません。
「病状が深刻だけれど、まわりの人の助けや会社からの特別な配慮があるおかげで、なんとか仕事を続けることができている」という客観的な事実を具体的に示すことができれば、障害年金を受け取れる可能性もあります。
大切なのは、働けているという事実だけでなく、「どれほどつらい病況で、どのようにまわりのサポートを受けながら仕事をしているのか」という具体的な状況を、医師の診断書やその他の書類でしっかりと伝えることです。
障害年金を働きながら受給するときのポイントは3つ
働いていても、障害等級にあてはまる病状であれば障害年金は受け取れます。
審査する人に正しい病状を伝えるためにできることは次の3つです。
- 医師と情報を共有し、診断書に正確な病状を記載してもらう
- 診断書の記載内容をチェックする
- 病歴・就労状況等申立書にフォロー体制や困りごとを的確に記載する
それぞれ見ていきましょう。
障害年金を働きながら受け取るには、障害等級にあてはまると国に認めてもらうことが必要です。
ご紹介した3つのポイントをすべて実践しても、障害等級にあてはまらないと判断され、「不支給」になることもあります。
(1)医師と情報を共有し、診断書に正確な病状を記載してもらう
働きながら障害年金を受け取るためには、診断書にあなたの病状や日常生活の困難さを正確に記載してもらうことが重要です。
障害年金の審査において医師が作成する診断書は、あなたの病状が障害年金の支給対象となる状態かどうか、どの程度の障害等級に該当するかを判断する上で、最も重要な書類の一つです。
たとえ、実際の病状が障害年金を受け取れるほどの重さであったとしても、診断書に軽い状態であると記載されてしまうと、障害年金が支給されないという結果になることもあります。
そのため、正確な診断書を作成してもらうためには、日頃から医師としっかりとコミュニケーションを取り、日常生活で困っていることや、家族やまわりの人からどのようなサポートを受けているかといった情報を具体的に伝えることが大切です。
医師にあなたの状況が正しく伝わることで、より実態に合った診断書が作成され、それが障害年金の適正な認定につながります。
(2)診断書の記載内容をチェックする
働きながら障害年金を受け取るためには、提出前に診断書の内容をしっかりと確認することが大切です。
医師が作成した診断書は、A3サイズの用紙の両面にわたって詳しく記載されるため、作成には時間と労力がかかります。
そのため、記載ミスや書き漏れなどが起こってしまうことも少なくありません。
もし、診断書の内容がご自身の病状や日常生活の困難さと比べて、軽く記載されていると感じたり、専門的な内容で正確に判断がつかない場合は、無理に自分で判断しようとせず、障害年金の申請手続きを専門家である社会保険労務士(社労士)に代行してもらうことも有効な手段の一つです。
社労士は、診断書の内容を専門的な視点から確認し、必要に応じて医師に修正を依頼したり、あなたの状況をより正確に伝えるためのアドバイスをしてくれます。
(3)病歴・就労状況等申立書にフォロー体制や困りごとを的確に記載する
働きながら障害年金を受け取るためには、「病歴・就労状況等申立書」で、あなたのふだんの生活や仕事でどのような困難があり、まわりからどのようなサポートを受けているかを具体的に伝えることが重要です。
医師が作成する診断書は、医学的な観点からあなたの病状や障害の状態を詳しく示すものです。
しかし、診断書だけでは、あなたが日常生活や職場で実際にどのようなことに困っているか、また、家族や友人、会社からどのような支援を受けているかといった具体的な状況までは十分に伝わりません。
そこで、「病歴・就労状況等申立書」という書類が、診断書を補完する役割を果たします。
この書類には、障害年金を申請するあなた自身が、ふだんの生活で困っていること、家族や友人など周囲から受けている具体的なサポートの内容などを詳しく記述します。
特に、障害者雇用で働いている、時短勤務をしている、仕事内容を限定してもらっているなど、会社から特別な配慮を受けている場合は、それがあなたが病気を抱えながらもなんとか就労を続けられている理由となります。
会社からの特別な配慮等を詳しく記載することで、障害年金を受給できる可能性が高まるでしょう。
もし、「病歴・就労状況等申立書」に何を書けば良いか分からない、どのように書けば自分の状況が正確に伝わるか不安な場合は、社会保険労務士(社労士)に申請手続きの代行を依頼し、書類を作成してもらうことができます。
.png)
病歴・就労状況等申立書については、下記の関連記事でさらに詳しくご紹介しています。
 病歴・就労状況等申立書の書き方は?基本の記入例から注意するべきポイントまで解説
病歴・就労状況等申立書の書き方は?基本の記入例から注意するべきポイントまで解説
障害年金を働きながら受け取るには、障害等級にあてはまると国に認めてもらうことが必要です。
ご紹介した3つのポイントをすべて実践しても、障害等級にあてはまらないと判断され、「不支給」になることもあります。
働きながら障害年金をもらう場合の年金額
障害年金は障害等級にあてはまる間は、「働いている」という理由で減額されることはありません。
令和7年度の障害年金の年金額は以下のとおりです。
| 障害の程度 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625 円+子の加算額 | 報酬比例の年金額×1.25 ※配偶者の加算あり |
| 2級 | 831,700円+子の加算額 | 報酬比例の年金額 ※配偶者の加算あり |
| 3級 | なし | 報酬比例の年金額 ※最低保証額623,800円 |
| 障害手当金 | なし | 報酬比例の年金額×2 ※支給は一度のみ |
報酬比例の年金額とは?
年金加入期間が長く、高い給与を受けていた人は年金額が多くなる年金
そのため、人によって金額が変わります
報酬比例の年金額は、誕生月に届く「ねんきん定期便」でおおよその年金額がわかるので、参考にしてみましょう。
障害年金の年金額の詳細は、下記の関連記事でご覧ください。
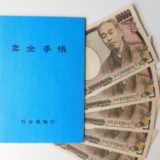 【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について
【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について
働きながら障害年金を受給できた事例
当事務所にご依頼いただき、働きながら障害年金を受給できた方の事例を2つご紹介します。
網膜色素変性症で障害厚生年金2級を取得し、次回更新まで約1,200万円を受給されたケース
- 相談者:30代男性
- 疾患名:網膜色素変性症
- 審査の結果:障害厚生年金2級
【相談者様の状況】
大学院卒業後に就職し、2年後に夜盲(暗いところで目が見えにくい)の症状が出始め、眼科を受診したところ網膜色素変性症と診断されました。
網膜色素変性症は治療法が確立されておらず、ビタミン剤や目薬を処方されるだけだったため、しばらく病院を受診していない期間がありました。
【サポート内容】
障害認定日から3か月以内にどこの病院も受診していなかったため、障害認定日の診断書を提出することができませんでした。
しかし、症状が悪くなることはあっても良くなることはないという不可逆性の病気であること、そして進行性の病気であることを根拠に、障害認定日で遡及ができるよう社労士が書類を作成しました。
なお、視野が狭まっていても視力は落ちていなかったので、職場では配置転換等の配慮を受け、正社員のフルタイム勤務を続けていました。
【審査の結果】
障害厚生年金2級が認められ、さらに次回更新まで約1,200万円を受給できることとなりました。
発達障害で障害厚生年金2級を取得し、次回更新まで約940万円を受給されたケース
- 相談者:40代男性
- 疾患名:発達障害
- 審査の結果:障害厚生年金2級
【相談者様の状況】
大学卒業後、就職するも仕事が思うようにできず、常に人間関係でトラブルを起こしていました。
40代になり発達障害専門医を受診して検査を受け、広汎性発達障害と診断されました。
障害者雇用枠で就職して5年目に障害年金受給を考えて、当事務所にサポートをご依頼くださいました。
【サポート内容】
障害者雇用枠ではありますが、給与は月に25万円以上、就労を5年以上継続できている、一人暮らしということで、障害年金を受給するには困難な状況でした。
働いているので、障害厚生年金3級を受給できるようにと慎重に進めていきました。
仕事での支障はもちろんですが、日常生活での支障がとても多く、友人等のサポートがなければ日常生活を送ることができないため、それを書面で記載しました。
【審査の結果】
結果は障害厚生年金2級、次回の更新年月は3年後という決定内容でした。

発達障害で就労できている方が障害厚生年金2級に認定されることは非常に稀なケースですが、実際にはあります。
このほかにも多くの事例がありますので、ぜひご覧ください。
まとめ
障害年金は3つの受給条件を満たしていれば、働いていても受け取ることができます。
人工透析や人工関節など、原則として障害等級の決まっている疾患や、検査で障害の程度が数値で測れる疾患は、審査の際に就労の有無が問題になることはありません。
一方で、うつ病やがんなどは検査で客観的に障害の程度を測ることができない疾患の場合は、診断書や病歴・就労状況等申立書で障害の状態や生活での困りごとを的確に記載することが大切です。
働きながら障害年金を受け取れるか不安な方や、書類の準備が難しいと感じる人は、ピオニー社会保険労務士事務所へご相談ください。
経験豊富な社労士が、あなたの障害年金申請をお手伝いします。