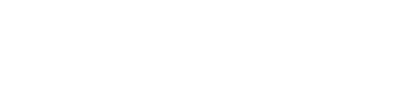脳出血は、脳卒中のひとつで日本人の死亡原因の第4位となる病気です。
毎年多くの人が脳出血で命を落としたり、後遺症で悩んでいますが、脳出血の原因について正しく理解している人は少ないようです。
そこで、この記事では脳出血の原因や予防法についてご紹介します。
脳出血での障害年金の受給や当事務所での受給事例もお知らせしますので、ぜひ最後までお読みください。
参考:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況(10ページ)|厚生労働省
目次
脳出血の原因はこの5つ!あなたも心当たりがある?
脳出血の原因としては、次の5つが原因として挙げられます
それぞれ見ていきましょう。
脳出血の原因(1)高血圧
高血圧は脳出血のもっとも多い原因です。
脳出血は、高血圧で発症する割合が最も高く、多くの患者に共通するリスク要因です。
血圧が高い状態が長く続くと、脳の細い血管に常に強い圧力がかかり、徐々に血管の壁がもろくなっていきます。
やがて、何かの拍子にその血管が破れてしまい、脳内に出血が起こるのです。
高血圧は自覚症状がほとんどないため、日頃からの血圧管理が非常に重要です。
脳出血の原因(2)動脈硬化による血管の老化
動脈硬化は脳出血の大きな原因のひとつです。
脳出血の原因にはいくつかありますが、血管の老化による動脈硬化も非常に重要なリスク要因です。
高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が進行すると、血管の内壁が硬くなり、弾力性を失います。これが動脈硬化です。
特に脳の細い血管では、動脈硬化が進むと血管壁がもろくなり、破れやすくなります。
さらに、動脈硬化が悪化すると「動脈瘤(どうみゃくりゅう)」と呼ばれる血管のこぶができ、それが破裂することで脳出血を起こすことがあります。
脳出血の原因として、動脈硬化は見逃せない存在といえるでしょう。
脳出血の原因(3)喫煙・飲酒などの生活習慣
乱れた生活習慣は脳出血の原因となるリスクを大きく高めます。
喫煙や過度な飲酒、不規則な食事、運動不足といった日常の習慣は、脳出血の原因となる高血圧や動脈硬化を悪化させる要因です。
特に喫煙は、血管を収縮させて血流を悪くし、血栓(血のかたまり)ができやすくなります。
これにより血管が詰まりやすくなり、結果として脳出血の原因となることがあります。
また、アルコールの摂りすぎは血圧の急上昇を招き、脳の血管に過剰な負担をかけます。
脳出血を予防するには、日々の生活習慣を見直し、体にやさしい選択を意識することが重要です。
脳出血の原因(4)ストレスや過労による血圧上昇
強いストレスや過労は、脳出血の原因となる血圧上昇を引き起こします。
ストレスを感じると、交感神経が活性化されて「ストレスホルモン」が分泌され、血管が収縮し血圧が上がります。
この血圧上昇が繰り返されることで、脳の血管に負担がかかり、脳出血の原因になってしまうのです。
さらに、慢性的なストレスや過労が続くと、血圧が常に高い状態になりやすく、ある日突然の強いストレスが引き金となって脳出血を発症することもあります。
脳出血の原因は生活習慣だけでなく、心の負担にも潜んでいるのです。
脳出血の原因(5)もやもや病などの病気
脳出血は中高年に多く発症しますが、30歳代の若い人でも次のような病気がある場合は脳出血を起こすことがあります。
【若い世代の脳出血の原因となる主な病気】
| 病名 | 特徴 | 脳出血との関係 |
|---|---|---|
| 脳動静脈奇形 | 動脈と静脈が異常なかたまりを作る先天性の疾患 | 若年者の脳出血の原因となることがある |
| もやもや病 | 脳の動脈が細くなり、細い血管が発達する | 細い血管が破綻すると脳内出血を引き起こす可能性がある |
| 脳動脈解離 | 脳動脈の内膜が裂けたり、血管の外側にふくらんで出血する | 脳梗塞や脳出血の原因になることがある |
上記のような病気が原因で脳出血を発症した場合、まず出血を止める治療が行われます。
その後、専門医のもとでそれぞれの病気にあった治療を行います。
参考:くまもと県脳卒中ノート|熊本県脳卒中・心臓病等総合支援センター
参考:脳血管障害・脳卒中|e-ヘルスネット(厚生労働省)
脳出血のリスクを高める要因とは?
脳出血のリスクを高める要因として挙げられるのは、加齢や性別、生活習慣などがあります。
また、急激な寒暖差があるときにも脳出血発症のリスクが高まるといわれています。
脳出血のリスクを高める要因を具体的に見ていきましょう。
年齢と性別により発症リスクが上がる
脳出血は、高齢者や男性が発症する割合が高いことが知られています。
厚生労働省が公表している「令和5年(2023)患者調査の概況」によると脳出血を含む脳血管疾患の患者数は以下のとおりです。
【脳血管疾患の患者数】
単位:千人
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 107.9 | 1.5 | 109.4 |
| 外来患者数 | 32.6 | 42.2 | 74.8 |
| 計 | 140.5 | 43.7 | 184.2 |
女性に比べて男性の患者数が約1.4倍となり、男性の方が脳血管疾患を発症しやすいことがわかります。
また、厚生労働省が公開する資料「脳血管疾患の性・病類・年齢(10歳階級)別粗死亡率(人口10万対)」によると年齢別の脳出血で死亡した人の割合は次のとおりです。
【脳出血の別粗死亡率】
(平成16年)
| 年代 | 39歳以下 | 40~49歳 | 59~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80~89歳 | 90歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡率 | 1.0 | 10.6 | 26.5 | 50.2 | 106.7 | 231.8 | 395.5 |
こちらのデータは、平成16年(2004年)のもので古いですが、現在でも中高年になるほどに脳出血での死亡率が高くなると推測されます。
食生活と運動習慣の関係
乱れた食生活や運動不足は、脳出血の原因として見過ごせない要素です。
特に、塩分の多い食事は高血圧を引き起こし、脳出血の大きな原因となります。
また、運動不足により血流が悪くなると、血管が硬くなってもろくなり、動脈硬化が進行します。
これが脳出血の原因になるケースも少なくありません。
さらに、運動をしない生活は肥満や糖尿病を招き、間接的に脳出血のリスクを高めることになります。
脳出血を防ぐには、バランスの取れた食事と、無理のない運動を日常に取り入れることが大切です。
日々の習慣こそが、脳出血の原因を遠ざける第一歩です。
寒暖差も影響
急激な寒暖差は血管に大きな負担をかけ、脳出血の原因になることがあります。
特に冬場は、寒さによって血管が急に縮み、血圧が一気に上昇しやすくなります。
この血圧の急変動が、脳の血管を破裂させる引き金となり、脳出血を引き起こす原因となるのです。
さらに、暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室へ移動する際の温度差による「ヒートショック」も、脳出血の重大な原因として知られています。
日常生活では、室温を一定に保つ工夫や、入浴前に浴室を暖めることが、脳出血を防ぐ対策として有効です。
気温の変化は見えないリスクとなるため、意識的な対策が必要といえます。
今日からできる脳出血の予防対策
脳出血は突然起こる病気ですが、生活習慣を変えるなどの予防策を取れば発症を防ぐことができます。
また、脳出血は、複数の要因が重なると発症しやすくなるといわれているので、ここでご紹介する対策を取って、脳出血発症の要因を減らしていきましょう。
血圧をコントロールする
脳出血を防ぐには高血圧にならないように予防することが大切です。
高血圧を防ぐ方法を以下にまとめました。
| 項目 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 減塩 | 薄味の味付けにしたり、醤油のかけすぎに注意するなどして減塩に努める |
| 野菜摂取 | カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂る例:ほうれん草、切干大根、干し柿、バナナなど |
| 適度な運動 | 軽めの有酸素運動を毎日行う例:早歩き、軽いジョギング、水中ウォーキングなど |
| 薬の服用 | 医師から処方された薬を用法・用量を守って正しく飲む |
高血圧の治療のために薬が処方されている場合は、スマホのタイマー機能を利用するなどして飲み忘れることがないように工夫するのもいいでしょう。
生活習慣を改善する
脳出血を予防するためには、生活習慣を改善することも欠かせません。
生活習慣の改善でできることは、次のようなことがあります。
| 生活習慣 | 改善策 | 効果 |
|---|---|---|
| 飲酒 | 週1〜2回の休肝日を設ける | 脳出血のリスクを低減 |
| 喫煙 | 禁煙する | 血管の健康を保つ |
| 食習慣 | 海藻や豆類なども積極的に食べて、バランスの取れた食事をとる | 高血圧や動脈硬化を防ぎ、脳出血のリスクを下げる |
これらの対策で生活習慣を改善できれば、脳出血の発症リスクを減らし、高血圧や糖尿病など生活習慣病の予防効果も期待できます。
ストレス管理と十分な睡眠
ストレスをためすぎないようにうまく発散したり、十分な睡眠をとったりすることで血圧を下げ、血管へのダメージを減らすことができます。
具体的な方法は下表のとおりです。
【ストレス管理】
ストレスをため過ぎないように、ふだんから次のようなことを生活に取り入れるのがおすすめです。
| 項目 | やること |
|---|---|
| 適度な運動 | ・ウォーキング(30分程度) ・ヨガ(ストレッチと深呼吸を組み合わせる) ・軽い筋トレ(スクワットやプランク)など 週3〜5回行うのが理想的 |
| リラックス法を身につける | ・深呼吸(4秒吸って7秒止め、8秒かけて吐く) ・瞑想(1日10分目を閉じて呼吸に集中) ・マインドフルネス 自分に合った方法をいくつかみつけておく |
| 趣味や楽しみの時間を持つ | ・読書、音楽鑑賞、映画・ドラマ鑑賞、ガーデニング、旅行、料理、絵を描く、楽器演奏など 1日のうちで、自分が楽しいと感じる時間を意識的に確保する |
【十分な睡眠】
睡眠の質を向上するためにできることは次のようなことです。
| 項目 | やること |
|---|---|
| 睡眠スケジュールの確立 | ・毎日同じ時間に寝起きする(理想は7〜8時間の睡眠) ・昼寝は20分以内にする |
| 快適な寝室環境 | ・部屋を暗くする(遮光カーテン使用) ・静かな環境を作る(耳栓やホワイトノイズを活用) ・室温は18〜22℃に保つ |
| 就寝前のリラックス | ・38~40℃のぬるめのお風呂に入る ・入浴は寝る1時間前が理想的 ・ストレッチ ・アロマオイルを活用する(ラベンダー、カモミールなど) |
ご紹介した方法がすべてできなくても、できることから始めてみましょう。
脳出血で障害が残ったら障害年金受給できることも
脳出血で麻痺などの障害が残った場合は、障害年金を申請できる可能性があります。
障害年金は、現役世代の人が病気やけがで障害を負ったときに申請できる制度です。
ピオニー社会保険労務士事務所では、脳出血での申請代行を数多くご依頼いただいています。
脳出血の障害年金申請を弊所にご依頼いただき、受給できた事例をご紹介します。
脳出血で障害厚生年金1級を受給できた事例
- ご相談者:40代男性
- 病 名:脳出血(橋出血)
- 認定結果:障害厚生年金1級
- 年金額: 約160万円
【ご相談時の状況】
脳出血で救急搬送された初診日から1年6か月経った頃に、ご本人から当事務所にご相談をいただきました。
四肢に麻痺が残り、左上下肢は痙縮やつっぱり感が強く、右上下肢も動きにくい状態になりました。
杖や装具を使用してゆっくりとなんとか歩行できる状態でしたが、ご本人に職場復帰したい希望が強く、すでに職場復帰をしていました。
【相談から申請までのサポート内容】
ご本人とお母様が面談にお越しくださり、左上下肢の重い麻痺と右上下肢の軽い麻痺から、肢体の障害で1級程度であると判断できました。
本来の障害認定日請求で、診断書作成を病院に依頼して3回の修正をサポートしました。
すでに職場復帰していましたので、診断書や病歴・就労状況等申立書にしっかりと職場での配慮や日常生活能力(ADL)を反映できるように努めました。
【審査の結果】
障害認定日で肢体の障害1級が認められました。
障害認定基準では1級は、一言でいうと「常時介護」です。
肢体の障害1級相当であってもフルタイムの仕事をしている方は多くいらっしゃいますので、必ずしも常時介護の状態でなくても認定されます。
なお、障害年金制度の概要や、障害認定日請求については以下の記事でわかりやすくご紹介しています。
 障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
 障害認定日請求とは|2通りの請求方法とできない場合の対処法
障害認定日請求とは|2通りの請求方法とできない場合の対処法
 脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
まとめ
脳出血の最も大きな原因は、高血圧です。
高血圧は、動脈硬化や喫煙、ストレスなどで悪化することが知られています。
脳出血は突然起こる病気ですが、高血圧や動脈硬化を予防できれば発症を抑えることができます。
生活習慣を整えたり、禁煙するなど、今日からできることから始めましょう。
もし、脳出血で障害が残り、生活に支障があるときは障害年金を受け取れる可能性があります。
脳出血での障害年金申請にお困りのときは、ピオニー社会保険労務士事務所へご相談ください。