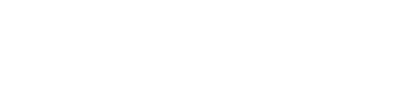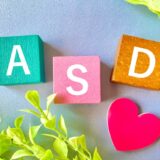障害年金は、病気やケガと向き合っている方の生活を支える大切な制度です。
しかし、受給には審査があり、その審査に通らなければたとえ該当する病気やケガを患っていても受給はできません。
残念ながら、近年では障害年金の不支給が増加しています。
そうなれば、日常生活に支障が出てしまうだけでなく、体力的あるいは精神的な負担も大きくなってしまうでしょう。
今回は、障害年金が不支給となる理由やその対策について詳しく解説していきます。
目次
障害年金の「不支給」が増加している背景
障害年金の申請数は年々増加していますが、同時に「不支給」も増加傾向にあります。
その背景として考えられるのは、以下2つです。
・審査基準の厳格化
・申請者自身の準備不足
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
審査基準の厳格化
障害年金の不支給が増えている背景の1つが、審査基準の厳格化です。
ご存じの方も多いと思いますが、現在は年金制度全体の財源不足が問題視されています。
このようなことから、本当に必要な方に支給を集中させる方向性が強まっており、これまで以上に障害年金の審査基準が厳しくなりつつあるのです。
例えば、同じ症状でも「日常生活にどの程度影響しているのか」が明確になっていない場合や、就労状況と診断書の記載が矛盾している場合などは不支給になることがあります。
申請者自身の準備不足
障害年金を受給するためには、必要書類を用意し、手続きを行わなければなりません。
しかし、必要な書類は多岐にわたり、手続きについてもかなり複雑なものとなるため、書類不備や手続き漏れなどが起こりやすいです。
特に、全ての作業を自分で行うとなると、上記のようなミスが起こりやすくなり、結果として「不支給」になってしまうことがあるため注意が必要です。
障害年金の受給申請については、社労士に依頼することもできますので、不安な場合はぜひ相談してみてください。
障害年金が「不支給」となる主な理由
障害年金が不支給となる理由としては、さまざまなことが考えられます。
代表的な理由は、以下の通りです。
・保険料納付要件を満たしていない
・初診日を証明できない
・障害年金の対象ではないと判断された
・書類に不備や矛盾がある
・障害状態がそこまで重くないと判断された
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
保険料納付要件を満たしていない
障害年金は、一定の保険料を納付している方を対象とした制度です。
何らかの理由があり、保険料の納付が免除となっている場合は問題ありませんが、一切手続きを行わず、保険料が未払いになっている場合は障害年金を受け取れません。
ちなみに、この場合は不支給ではなく「却下」という扱いになります。
不支給とは、審査が最後まで終わった結果「支給しない」という結論に至った状態のことです。
一方、却下とは審査に入る前に門前払いされてしまう状態を指します。
つまり、保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金支給審査の土俵にも上がれないということです。
初診日を証明できない
障害年金を受給するためには、初診日を証明する必要があります。
初診日とは、対象となる病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことです。
これは、単なる自己申告では認められず、受診状況等証明書を医療機関に発行してもらわなければなりません。
初診日を証明できない場合、こちらも不支給ではなく却下となります。
ただ、初診日の特定は意外と難易度が高く、
・初診で訪れた病院が廃院となっていた
・カルテの保存期間が過ぎていた
など、さまざまな理由で入手が難航する場合があります。
このようなケースでは、受診状況等証明書を添付できない旨を記載した申立書を作成したり、2番目以降に診察を受けた医療機関で証明してもらったりといった方法で対応するのが一般的です。
障害年金の対象ではないと判断された
障害年金は、全ての病気やケガに対して支給されるわけではありません。
また、対象となる病気やケガを患っていたとしても、障害の程度が軽いと判断された場合、不支給になる可能性が高いです。
例えば、軽度の症状であり、継続的な治療によって十分な改善が見込まれるケースでは不支給になることもあります。
また、発達障害や精神疾患など、明確に証明するのが難しい疾患の場合、診断書や申立書の記載が不十分だと「不支給」になりやすいです。
書類に不備や矛盾がある
障害年金を受給するためには、さまざまな書類を用意しなければなりません。
1つでも書類が漏れていたり、内容に不備が合ったりすると不支給になる可能性が高まります。
また、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に食い違いがあると、信ぴょう性が低いと判断され、結果として不支給になることがあるため注意が必要です。
障害年金は国の制度であり、些細な記入漏れや誤字でも不支給になる場合がありますので、書類作成は慎重に行いましょう。
障害状態がそこまで重くないと判断された
障害年金は、病気やケガによって就労が困難になった際に適用される制度です。
そのため、会社員やパートとして働いていて、一定以上の収入を得ている場合、障害状態がそこまで重くない(日常生活に大きな支障がない)と判断され、不支給になる場合があります。
中には、一定の所得があると障害年金は受け取れないと考える方もいますが、一定の所得があることで障害年金が不支給になることはありません。
ただし「働けている=障害状態が軽い」と判断される可能性があることもまた事実ですので、ぜひ覚えておいてください。
障害年金が「不支給」となった場合の対処法
障害年金が不支給になると、生活に大きな支障が出る場合があります。
そのため、早急に対処しなければなりません。
ここからは、不支給決定通知書(却下通知書)が届いた後にやるべきことを紹介していきます。
不支給の理由を確認する
障害年金が不支給となった場合、まず行うべきなのが「理由を確認すること」です。
障害年金の不支給決定通知書には、不支給となった理由が簡単に記載されています。
不支給となった理由が書類不備なのか、障害の程度なのか、初診日の証明についてなのかによって、今後の対応が大きく変わりますので、必ず確認しましょう。
ただし、通知書に記載されている理由は簡潔にまとめられていることが多く、詳細な審査過程や基準については明記されていないこともあります。
その場合は、保有個人情報開示請求で詳しい情報を入手するのがおすすめです。
ただし、これにはさまざまな書類を準備したり、手続きをしたりといった手間がかかるため、社労士への依頼を検討しましょう。
不服申立てを行う
障害年金の不支給決定に納得がいかない場合は、不服申し立てを行えます。
不服申立てには、
・審査請求
・再審査請求
上記2つの種類があります。
審査請求とは、障害年金申請時に提出した書類の再審を求める方法です。
再審査請求とは、必要書類などを見直し、新たに提出して審査を受ける方法です。
障害年金が不支給となった場合は、ひとまず審査請求を行い、そこでも認められなければ再審査請求を行うという流れになります。
審査請求では、審査請求書の書き方がとても重要になるため、社労士をはじめとする専門家に相談しながら作成していくことをおすすめします。
障害年金の不支給を避けるためのポイント
障害年金が不支給となった場合でも、適切に対処すれば受給できる可能性が高まります。
しかし、一度不支給になると、その理由を確認したり、不服申し立てをしたりとやるべきことが増えてしまうため、できるだけ不支給を避けるための工夫を行うことが大切です。
ここからは、障害年金の不支給を避けるためのポイントを紹介していきます。
早めに初診日を特定する
障害年金を受給するためには、初診日をしっかりと証明しなければなりません。
初診日とは、該当する病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことであり、初診日を証明できないと不支給になる可能性が高まります。
しかし、初診日の証明は意外と難しく、
・初診で訪れた病院が廃院となっていた
・カルテの保管期限を過ぎていた
など、不測のトラブルが起こるケースもあります。
場合によっては、過去に通った病院を全て洗い出す必要が出ることもあるため、早めに準備を進めるのがおすすめです。
診断書の依頼は慎重に行う
障害年金の審査では、診断書が最も重要な判断材料となります。
しかし、医師によっては障害年金制度に詳しくなく、適切な情報を記載してもらえなかったり、そもそも診断書の作成を拒否されたりすることもあります。
そうなれば、障害年金の申請に時間がかかってしまうため、日常生活にどれほどの影響が出ているかを具体的に説明すると同時に、障害年金用の診断書を作ってもらいたい旨をハッキリ伝えるようにしましょう。
日常生活における支障を具体的に記録する
障害年金の受給審査では、日常生活への影響を重点的に見られます。
そのため、普段の生活の中でどのような支障があるのかを具体的に記録しておくことが大切です。
・一人で買い物に行けない
・電車での移動が困難
・家から出ようとすると腹痛に襲われる
など、具体的な状況やシーンをメモしておくことで、書類作成をスムーズに進めやすくなります。
社労士に相談する
障害年金の不支給を避ける上で最も効果的なのは、社労士に相談することです。
自分自身で書類の用意から手続きまでを進めることも可能なのですが、この場合は書類不備や記入漏れが起こりやすくなり、結果として不支給のリスクが高まります。
障害年金に精通した社労士に相談することで、ほぼ全ての手続きを代行してもらえるようになり、必要に応じてアドバイスや提案をしてもらえるため、スムーズに手続きを進めやすくなります。
障害年金の申請を社労士に依頼するメリット
障害年金の申請を社労士に依頼するメリットは、以下の通りです。
・手続きを丸ごと任せられる
・医師とのやり取りがスムーズになる
・状況に応じたアドバイスや提案をしてもらえる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
手続きを丸ごと任せられる
障害年金は、制度の仕組みがとても複雑であり、申請においてはさまざまな書類が必要になります。
また、国の制度ということもあり、ちょっとしたミスで不支給あるいは却下になる可能性があるため、慎重に準備を進めていかなければなりません。
特に、初めて障害年金を申請する方や、障害年金に関する知識がない方の場合、書類不備や記入漏れといったミスが起こりやすいため注意が必要です。
社労士に依頼した場合、書類の手配から実際の手続きまでを丸ごと任せられるため、スムーズに手続きを進められます。
同時に、書類の用意や記入といった手間を省けるため、忙しい方でも安心です。
医師とのやり取りがスムーズになる
障害年金を受給するためには、医師から診断書を発行してもらわなければなりません。
しかし、診断書の内容が障害年金に適していない場合や、そもそも診断書の作成を拒否されたりする場合もあります。
社労士に相談することで、診断書の修正依頼や補足説明などをサポートしてもらえるようになります。
申請者と医師の間に入ってコミュニケーションを取ってくれることは、社労士に相談する大きなメリットといえるでしょう。
状況に応じたアドバイスや提案をしてもらえる
障害年金に精通した社労士は、これまでの経験や申請事例を基に、状況に応じたアドバイスや提案をしてくれます。
仮に不支給になったとしても、その原因や対処法を丁寧に模索してくれるため、安心して任せられます。
また、症状の程度や生活状況をどのように伝えるべきかといった戦略的なアドバイスもしてくれるため、最後まで安心して手続きを進めたい方は、ぜひ社労士への依頼を検討してみてください。
障害年金のことなら「ピオニー社会保険労務士事務所」にお任せください!
障害年金が不支給になる理由はさまざまですが、中でも「自分で全ての手続きを行う場合」は、不支給になる可能性がグッと高まります。
なぜなら、書類不備や記入漏れといったケアレスミスが起こりやすいからです。
ピオニー社会保険労務士事務所では、障害年金を専門に取り扱っており、これまでにも3,000件以上の対応実績があります。
受給率は99%以上となっており、他の社労士事務所で断られた案件にも対応可能です。
ご依頼後は、進捗を密に連絡し、手続き完了までご依頼者様を不安にさせないための工夫を行っていますので、安心してお任せいただけます。
現在では、無料受給判定も行っていますので、障害年金のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。
まとめ
障害年金は、生活や就労に大きな支障を抱える方の支えとなる重要な制度です。
しかし、実際には「不支給」や「却下」といった結果に至るケースも少なくありません。
その背景には、審査の厳格化や書類不備、準備不足といったさまざまな理由がありますが、いずれも制度特有の「複雑さ」が大きく関係しています。
不支給や却下を避け、スムーズに障害年金の申請を行うためには、その道のプロである社労士に相談するのがおすすめです。
障害年金専門の「ピオニー社会保険労務士事務所」でも、障害年金の申請サポートを行っていますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。