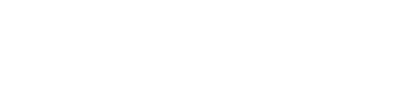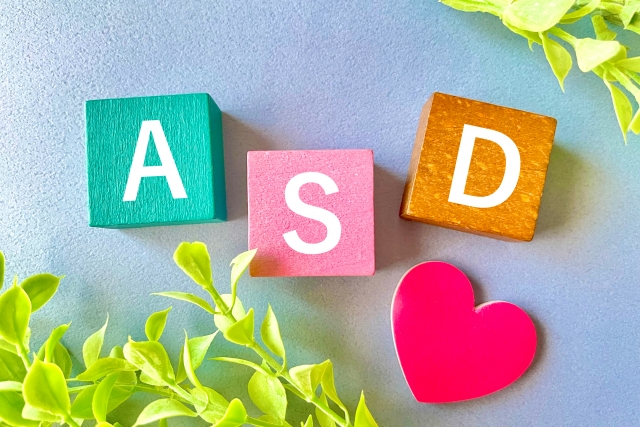自閉症スペクトラム障害は、先天的な中枢神経系の機能障害です。
コミュニケーション能力の欠如や言語の発達遅延、反復行動や他害行為など、症状やその程度は人によってさまざまですが、場合によっては就業が困難になってしまうケースもあります。
そんなときは、障害年金を申請してみましょう。
自閉症スペクトラム障害は、発達障害の一種であり、申請をすれば障害年金を受け取れる可能性があります。
そこで今回は、自閉症スペクトラム障害の方が障害年金を受給する際のポイントや条件などについて、詳しく解説していきます。
目次
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に大きな支障が出たときに支給される公的年金制度です。
これは、病気やケガと向き合う方の生活を支えるとても重要な制度ですが、その仕組みはとても複雑であり、多くの方がさまざまな疑問や不安を抱えています。
障害年金を受け取り、生活への負担を軽減するためには、制度に関する正しい知識を身につけておくことが大切です。
ここからは、障害年金の基本的な仕組みや自閉症スペクトラム障害との関係について詳しく解説していきます。
障害基礎年金と障害厚生年金について
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金は、国民年金に加入している方が対象です。
初診日が国民年金加入中となっている場合、この基礎年金を受給することになります。
対象者は、主に自営業者や学生、無職の方であり、障害の等級が1級または2級に該当する場合に支給されます。
一方、障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
会社員や公務員などは、基本的に厚生年金の対象となります。
こちらは1~3級までの障害等級が存在しており、3級に該当している場合でも受給可能です。
自閉症スペクトラム障害(ASD)と障害年金について
障害年金は、国が定める基準を満たしている方のみに支給されます。
そこで気になるのが「自閉症スペクトラム障害は受給対象になるのか」ということですよね。
結論からお伝えすると、自閉症スペクトラム障害も障害年金の受給対象となります。
ただし、全ての方が無条件で受け取れるわけではなく、国が行う審査を通過しなければなりません。
障害年金の審査では、
・対人関係が極端に苦手で就労が難しい
・日常の金銭管理ができない
といった実生活の支障があるかを重点的にチェックします。
つまり、自閉症スペクトラム障害であること自体よりも、生活能力の低下度合いが受給の可否を左右するのです。
自閉症スペクトラム障害(ASD)の認定基準
障害年金では、傷病によって認定基準が設けられており、スペクトラム障害の場合は「発達障害」の認定基準が適用されます。
【発達障害における認定基準】
1級:発達障害があり、社会コミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適当な行動が見られるため、日常生活への適応が困難であり常時援助を必要とするもの
2級:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適当な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が見られ、労働が著しく制限されているもの
上記の等級は、診断書の記載事項となっている「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」によって定められています。
障害厚生年金の場合は、1~3級に該当する方が対象となり、基礎年金の場合は1~2級に該当する方が対象となります。
自閉症スペクトラム障害(ASD)で障害年金を受け取るときのポイント
自閉症スペクトラム障害の方が障害年金を受け取るためのポイントは、以下の通りです。
・初診日の証明が重要
・年金保険料を納めていなければ受け取れない
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
初診日の証明が重要
障害年金の申請では「初診日」が極めて重要です。
初診日とは、自閉症スペクトラム障害のために初めて医療機関を受診した日のことを指します。
自閉症スペクトラム障害は先天性の疾患であり、中には「生まれた日が初診日である」と勘違いをしてしまう方もいるのですが、スペクトラム障害の何らかの症状で医療機関を受診した日が「初診日」となります。
例えば、幼少期から自閉症スペクトラム障害のような症状があったとしても、病院を受診することなく成長し、大人になってから自閉症スペクトラム障害の症状で医療機関を受診した場合、その日が「初診日」です。
また、自閉症スペクトラム障害は初診日の証明に時間を要するケースもあります。
・初診で訪れた病院が廃院していた
・カルテの保管期限を過ぎていた
・複数の病院を受診していて、どれが初診かわからない
このように、書類を準備する上でトラブルが起こることもあるため、時間に余裕を持ってじっくり準備を進めていきましょう。
年金保険料を納めていなければ受け取れない
障害年金は、社会保険制度の一種であるため、一定の保険料を納めていなければ受給資格を得られません。
1:初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間で、保険料を納めた期間が被保険者期間の3分の2以上である
2:初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間がない
上記の条件を満たしていない場合、障害年金を受給できないため注意が必要です。
ただし、初診日が20歳未満である場合は例外となり、保険料の納付は要求されません。
障害年金の審査で重要視される2つの書類
障害年金を受け取るためには、審査を受ける必要があります。
その審査で重要視されるのは、以下2つの書類です。
・診断書
・病歴・就労状況申立書
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
診断書
診断書は、障害年金において「核」となる存在です。
等級判定ガイドラインには、診断書の記載事項を基に等級の目安が定められており、診断書の内容で等級が決まるといっても過言ではありません。
同時に、診断書は医師が作成する信頼性の高い書類であり、障害年金の受給対象かどうかを審査する上でとても重要になるのです。
また、診断書には日常生活の困難さや支障を記載してもらう必要があり、内容が不十分もしくは分かりにくい場合、等級が下がったり、障害年金を受給できなくなったりすることがあります。
このような事態を避けるためには、医師に現状を説明し、日常生活への支障を正しく記載してもらえるように依頼することが大切です。
病歴・就労状況等申立書
診断書と同じくらい重要なのが、病歴・就労状況等申立書です。
これは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するための書類であり、申請者本人が記載する必要があります。
日常生活にどのような支障が出ているのかを自分で説明できる「唯一の書類」となるため、書き方や書くべき内容などを事前に調べ、しっかりと記載することが大切です。
【病歴・就労状況等申立書を書くときのポイント】
・できるだけ具体的に書く
・出生から現在までの状況を3~5年に分けて記載する
・診断書の内容と相違が無いようにする
自閉症スペクトラム障害(ASD)の障害年金申請でよくある落とし穴
自閉症スペクトラム障害における障害年金申請では、さまざまな手続きが必要であり、それに伴って複数の書類が必要になります。
特に初診日の証明や診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の書き方については、多くの方が苦労するポイントです。
また、準備不足や書類不備によって不支給となるケースもあるため、注意が必要です。
ここでは、障害年金申請におけるよくある落とし穴と、その対策について詳しく解説していきます。
初診日の証明ができない
先ほども解説したように、障害年金の受給申請においては「初診日の証明」がとても重要です。
しかし、自閉症スペクトラム障害は幼少期から症状が見られるケースもあり、どの時点を「初診日」とするかが不明確になりがちです。
また、通っていた病院が閉院となっていたり、カルテが破棄されていたりして証明が難しくなるケースもあります。
そのような場合は、通っていた学校の記録や療育手帳の履歴など、医療機関以外の証拠を活用するなど、別の方法を検討しなければなりません。(第三者証明)
ただし、第三者証明は20歳前に初診日がある場合と、20歳以降に初診日がある場合で扱いが異なるため、どうしても初診日の証明ができない場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
医師が診断書を書いてくれない
障害年金の申請で重要になる診断書ですが、稀に医師が診断書を作成してくれない場合があります。
これにはさまざまな理由がありますが、診断書がなければ受給申請ができません。
そのため、日常生活への支障などを具体的に伝え、診断書を作成してもらえるように話し合いを進めていく必要があります。
どうしても診断書を作成してもらえない場合は、転院を検討するか、障害年金に精通した社労士に相談して、間に入ってもらいましょう。
病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない
病歴・就労状況等申立書は、日常生活における支障を自ら説明できる唯一の書類です。
しかし、
・どこまで詳しく書けばいいのか
・どの表現が適切か
・どの内容をどの順番で書けばいいのか
といった疑問が生じるケースも珍しくありません。
この書類は、審査側に「日常生活において大きな支障が出ている」ことを説明するための書類であり、内容が伝わらなければ意味がないため、正しい書き方を覚えておく必要があります。
基本的には、全てにおいて「具体的に書く」ことを意識しつつ、診断書の内容と整合性を取ることが大切です。
どうしても書き方がわからない場合は、社労士などに相談してアドバイスをしてもらいましょう。
障害年金を支給してもらえなかった
書類を全て揃え、手続きを完了させたからといって、必ずしも障害年金を受給できるとは限りません。
場合によっては、審査の段階で不支給もしくは却下(審査すらされない)になってしまうこともあります。
そうなれば、障害年金を受け取れなくなってしまうため、事前に対策をしておくことが大切です。
不支給もしくは却下になる理由や対処法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
 障害年金の「不支給」が増加中?受け取れない理由と対策を徹底解説!
障害年金の「不支給」が増加中?受け取れない理由と対策を徹底解説!
自閉症スペクトラム障害(ASD)の障害年金申請は社労士に依頼すべき?
障害年金の制度はとても複雑であり、申請に必要な書類や手続きも多岐にわたります。
そこで役立つのが、社会保険労務士の存在です。
ここでは、社労士に障害年金の申請を依頼するメリットを3つ紹介していきます。
メリット1:手続きを丸ごと任せられる
障害年金の申請では、初診日の確認・診断書や申立書の準備・年金事務所とのやり取りなど、多くの手続きが発生します。
これらの手続きを全て自分で行うのは中々大変です。
場合によっては、途中で挫折してしまうこともあります。
社労士に依頼することで、障害年金の申請に関するほぼ全ての手続きを任せられるため、申請者の負担を大幅に軽減できます。
また、必要書類の準備不足や記入漏れなども防げるため、スムーズに申請が行えます。
メリット2:医師とのやり取りがスムーズになる
診断書は、障害年金の申請においてとても重要な書類です。
しかし、医師が障害年金制度に詳しくない場合、記載内容が実態に合わないまま提出され、不支給になることがあります。
このような場合、社労士が医師に対して「どういった観点で診断書を書いて欲しいのか」を適切に伝えてくれます。
また、状況に応じて補足資料の添付を依頼したり、本人に代わって医師に日常生活の支障を伝えてくれたりするため、障害年金でよくある「診断書をめぐるトラブル」を防ぎやすくなるのです。
メリット3:状況に応じたアドバイスや提案をしてもらえる
障害年金の申請は、一般の方にとって非常に難易度の高い作業です。
全体の流れがわからなかったり、書類の書き方で悩んでしまったりすることもよくあります。
社労士に相談することで、全体の流れをわかりやすく説明してもらえるだけでなく、そのときのフェーズに合った適切なアドバイスや指示をもらえるため、素早くそしてスムーズに手続きを進められるようになります。
「いつでも専門家に相談できる」という安心感を得られることも、社労士に相談するメリットの1つです。
障害年金のことなら「ピオニー社会保険労務士事務所」にお任せください!
自閉症スペクトラム障害は障害年金の対象となる疾患ですが、受給するためにはさまざまな書類を用意し、複雑な手続きを行わなければなりません。
万が一、必要な書類が漏れていたり、内容に不備が合ったりすると、不支給もしくは却下になってしまいます。
このような事態を避け、スムーズに申請を行うためには、障害年金に精通した社労士に相談するのがおすすめです。
ピオニー社会保険労務士事務所は、障害年金を専門としており、3,000件を超える相談実績があります。
受給実績は99%で、他の社労士事務所で断られた案件にも対応しています。
「そもそも障害年金を受給できるのかどうかわからないんだけど・・・」
という方に向けて、無料受給判定も行っていますので、障害年金のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。
まとめ
自閉症スペクトラム障害は発達障害の1つであり、障害年金の支給対象です。
しかし、自閉症スペクトラム障害と診断されたからといって無条件で障害年金を受給できるわけではなく、さまざまな書類を準備した上で手続きを行わなければなりません。
もちろん、書類の用意から手続きまでを全て自分で行うこともできますが、知識がない方にとっては非常に難易度が高い作業となります。
スムーズに障害年金の申請を行いたい場合は、その道のプロである「社労士」に相談するのがおすすめです。
障害年金専門の社労士事務所「ピオニー」では、無料受給判定や無料相談を行っていますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。