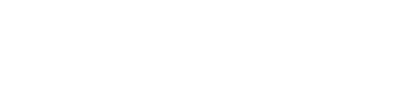障害年金の申請をしようと考えたときに、ご自分で申請準備を進めるか、専門の社労士に申請の代行を依頼するか迷う方も多いと思います。
ご自分で申請ができる場合には、わざわざお金をかけてまで社労士に代行を依頼する必要はありません。
しかし、「初診日がどうしても証明できない場合」や「医師が診断書を書いてくれない場合」などは、ご自分で申請準備を進められないケースも出てきます。
そこでこの記事では、ご自分で障害年金の申請をしても大丈夫かを見極めるためのチェックリストと、社労士に依頼した方がいいケースなどについてご紹介します。
障害年金の申請を進める前に、まずはこの記事を最後まで読んでチェック項目を確認してみましょう。
目次
障害年金はいつから申請できる?
障害年金の申請開始の時期は「障害認定日」以降です。
障害年金は遅くなっても申請できますが、たとえ早い時期に診断名が確定しても、障害認定日が到達するまで待つことになります。
- 初診日※1から1年6か月が過ぎた日
※1 「初診日」とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関で診療を受けた日
- 初診日から1年6か月到達前に治った※2日
※2 「治った」とは、治療の効果がないと認めらること(完治を指すものではない)

スムーズな申請のために、障害認定日がまだ先でも初診日はいつなのかを証明する書類を探したり、通院歴をまとめておくことをおすすめします。
なお、障害年金申請の流れは、障害年金申請の流れとは?7つのステップで徹底解説でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
障害年金は「請求」するものですが、この記事では一般的に浸透している表現を採用し「申請」すると表記します。
障害年金、自分でも申請できる?6つのポイントで簡単チェック!
障害年金は、次の6つの項目をクリアできれば、自分で申請できます。
それぞれご紹介していきますので、ご自身で申請できるか確認してみましょう。
チェック(1):ご自身の今の状況は?
障害年金を申請する本人のチェックポイントは、以下のとおりです。
- 自分(もしくは家族)が障害年金の申請準備に多くの時間と労力をかける余裕がある
- 現在の障害の病名がはっきりしている
障害年金の申請には、多くの時間と労力がかかります。
ご自分で申請する場合は、申請準備にかかる時間は早くても数か月、その間に何度も年金事務所や市区町村役場に通う必要があります。
障害年金の申請のために、こういった時間や手間をかけることができるのか、ご自身の状況を振り返ってみましょう。
また、現在の障害の診断名がはっきりしていることも必須項目です。
長く通院している場合でも、主治医からはっきりと病名を聞かされていないことがあります。
さらに、転院を繰り返している場合、「1番目の病院では不安神経症、2番目の病院では自律神経失調症と診断」され、「現在通院している病院では病名を言われていない」というような複雑なケースもあり、注意が必要です。
チェック(2):初診日について
障害年金は「初診日」が証明できないと申請できません。
初診日に関するチェックリストは以下のとおりです。
- 障害年金でいう初診日とは、「診断名がついた病院に初めて行った日」ではないことが理解できる
- 初診日に受診した病院名を覚えている
- 初診日に受診した病院に、当時のカルテがまだ保管されている
- 初診日をしっかりと覚えている
- 初診日の前日において保険料納付要件を満たしている
- 初診日となりそうな日が複数あっても、根拠を持ってどの初診日を主張するのが妥当なのかがわかる
障害年金の初診日は、「その障害の症状が出て初めて病院に行った日」です。
転院を繰り返している方の場合、診断名がついた病院を初めて受診した日が初診日になるとは限りませんので、注意しましょう。
よくあるケースとしては、初診日がかなり前にあり、病院名も受診した日付も覚えていないというものです。
まずはどの病院に行ったのかがわからないと初診日の証明もできませんので、初診日に受診した病院を覚えていることはとても重要です。
初診の病院から転院をしている方は、初診から現在までの通院歴をまとめておきましょう。
【ずっと前に病院を受診していたけれど、その後は治療の必要がなく長期間普通に社会生活を送っていた場合】
上記のような場合には、「再発して病院を初めて受診した日を初診日」として主張できることがあります。
この場合には、しっかりと根拠や証拠を元に主張しなければなりません。
このように「障害年金での初診日」は、「一般的な感覚で見る初診日」とは違うケースがが多くあります。
初診日について正しく理解できない場合は、ご自身で障害年金を申請するのは難しいといえるでしょう。
障害年金での「初診日」の捉え方や証明方法、受診状況等証明書については、関連記事でわかりやすくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
 障害年金における「初診日」とは?初診日の重要性や証明方法も併せて解説
障害年金における「初診日」とは?初診日の重要性や証明方法も併せて解説
 受診状況等証明書がないと障害年金はもらえない?作成できる医療機関もご紹介
受診状況等証明書がないと障害年金はもらえない?作成できる医療機関もご紹介
チェック(3):障害認定日や遡求について
障害認定日や遡及請求についてのチェック項目は次のとおりです。
- 初診日から1年6か月経過している場合、遡及請求できる日付(障害認定日)がわかる
- 障害認定日時点で障害年金を受給できる障害の程度であるかどうかを自分で判断できる
- 障害認定日ごろに通院していた病院で当時のカルテがまだ保管されている
- 現在は障害認定日に通院していた病院から転院している場合、障害認定日の診断書作成を依頼する望ましい方法が自分でわかる
- 遡及請求する場合、障害認定日から現在までに症状が軽くなったり、働けていたりする期間はない
障害年金の申請は、原則として初診日から1年6か月経過した日が「障害認定日」になります。
ただし、障害の種類によっては「障害認定日の特例」があり、初診日から1年6か月経たずに障害認定日請求することができます。
障害認定日請求をする場合には、ただ診断書を提出すればいいというものではなく、障害認定日に国で定めている基準(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)に該当していることが重要になります。
障害認定日請求をする際に添付する診断書は、医師がカルテに基づいて作成します。
したがって、カルテが破棄されていたり病院が廃院している場合、診断書を作成していただくことができません。

現在通院中の病院であれば、医師が現在の状況を把握しているため診断書の依頼がしやすいですが、過去に通院していた病院に依頼する場合、作成を断られることもあります。
【遡及請求をする場合】
障害認定日に遡って請求(遡及請求)する場合は、障害認定日から現在までの症状の変化や就労状況も審査の対象となります。
そのため、障害認定日から現在までに問題なく働けている場合は、審査に影響する可能性があるため注意が必要です。
障害認定日請求や、遡及請求について正確な知識がない場合は、ご自身で申請することは困難といえます。
なお、遡及請求や障害認定日請求の詳細は関連記事でご紹介していますので、ぜひお目通しください。
 障害年金で数百万円がもらえる遡及請求とは?
障害年金で数百万円がもらえる遡及請求とは?
 障害認定日請求とは|2通りの請求方法とできない場合の対処法
障害認定日請求とは|2通りの請求方法とできない場合の対処法
チェック(4):現在の障害状態について
現在の障害の程度についてのチェックポイントは次のとおりです。
- 現在の状態は、障害年金を受給できる障害の程度であるかどうかを自分で判断できる
単に病名がついただけでは障害年金は受給できません。
現在の症状が国で定めている基準(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)に該当していることが必須条件になります。
障害年金の等級ごとの認定基準については関連記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
 障害年金の等級とは?等級ごとの具体的な認定基準や等級変更について徹底解説
障害年金の等級とは?等級ごとの具体的な認定基準や等級変更について徹底解説
チェック(5):診断書や病院対応について
障害年金の申請書類には主治医の作成する「診断書」があり、主治医や病院とやり取りをすることは避けられません。
診断書や病院対応についてのチェックポイントは以下のようになります。
- 受診状況等証明書や診断書の作成を病院に依頼する際、病院側が理解を示さなくても自分で説明したり主張したりすることができる
- 診断書を見て不備があるかどうか理解でき、不備があった場合には自分で病院側に伝えることができる
- 出来上がった診断書を見て、障害年金が受給できる内容であるか、受給できるとするならば何級相当になるのかが理解できる
病院の中には、「障害年金の受診状況等証明書や診断書を書いたことがない」というところもあります。

病院から書類の作成を断られることもありますし、書き方について質問されることもあります。
また診断書に不備があった場合には修正依頼をしなければならず、病院とのやり取りは申請者にとって大きなストレスとなるでしょう。
特に重要なのは、出来上がった診断書の内容を申請者自身が確認することです。
診断書に不備がないか、障害の状態が正しく反映されているかを見極めなければなりません。
もし修正が必要な場合は、「なぜ修正が必要なのか」「どこをどう修正するのか」を病院側に明確に説明する必要があります。
なぜこのようにきめ細やかな確認と修正依頼が必要なのかというと、診断書の内容が国が定めた基準に合致していなければ、診断書を年金事務所等に提出しても意味がないからです。
さらに、障害認定基準に該当しているならば何級相当なのかが把握できると、年金受給の見込みが立ち、希望を持って申請に臨むことができます。
なお、診断書についてもっと知りたい方は関連記事をご覧ください。
 障害年金の診断書について徹底解説【完全初心者向け】
障害年金の診断書について徹底解説【完全初心者向け】
関連記事:障害年金の診断書について徹底解説【完全初心者向け】
チェック(6):病歴・就労状況等申立書の作成について
障害年金の申請時には「病歴・就労状況等申立書」を添付します。
「病歴・就労状況等申立書」は申請者が作成する書類ですが、「難しくて書けない」というお声を耳にすることが多いです。
以下のチェック項目を見て、ご自身で作成できるか確認しましょう。
- 病歴・就労状況等申立書の基本的な書き方がわかる
- 病歴・就労状況等申立書に書いたほうがよい内容、書かなくてよい内容がわかる
- 「受診状況等証明書」と「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の整合性を取ることができる
- 診断書の内容が薄い場合に、それを病歴・就労状況等申立書で補う方法がわかる
結論からお伝えすると、病歴・就労状況等申立書は、ルールに従って作成しなければなりません。
病歴・就労状況等申立書に、今困っていることやつらい気持ちなどをたくさん書いてしまうケースが見られますが、自分の心情や困りごとを記載しても、障害年金の審査にはプラスになりません。
書くべき内容を読みやすく簡潔に、わかりやすい文章で書くとよいでしょう。
また、よくあるケースとして「診断書に書かれていることと病歴・就労状況等申立書の内容が食い違っている」ことが挙げられます。
「受診状況等証明書」と「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の3つの書類は、整合性を取ることが大切です。
受診状況等証明書や診断書に書いてあることに相違がある場合には病歴・就労状況等申立書で補完するようにしてください。
なお、診断書に実際の障害状態が正しく反映されていない場合でも、申立書で詳細を補うように記載することで、正しい等級で障害年金を受給できる可能性があります。
それほど、病歴・就労状況等申立書は重要な役割を担っていることがお分かりいただけるでしょう。
病歴・就労状況等申立書の書き方や作成の注意点の詳細は、下記の関連記事を参考にしてください。
 病歴・就労状況等申立書の書き方は?基本の記入例から注意するべきポイントまで解説
病歴・就労状況等申立書の書き方は?基本の記入例から注意するべきポイントまで解説
障害年金の申請を社労士に依頼した方がいいケース
障害年金の申請を社労士に依頼した方がいいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 初診日の証明が難しい
- 障害年金の申請を早くしたい
- 精神疾患などで療養に専念したい
- 難病など難易度の高い疾患で申請する
上記のようなケースの場合、ご自分で申請すると申請までの時間が非常にかかったり、書類不備になり不支給になったりする可能性がとても高いです。
お早めに障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。
障害年金の申請を社労士に依頼するメリット
障害年金の申請をご自分でするか、社労士に依頼するかで迷われている方もまだ多いと思います。
障害年金の申請代行を社労士に依頼するメリットをまとめました。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 手間の軽減 | ・必要書類(受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書など)の収集や作成を社労士が代行 ・通院や療養に専念できる。 |
| 受給開始が早い | ・書類の不備を防ぎ、手続きの効率化により、受給までの期間を短縮 ・不備による修正の繰り返しで受給が遅れるリスクを低減 |
| 不支給リスクの低減 | ・専門知識を活用して、本来の等級よりも低い等級での認定や不支給リスクを最小限に縮小できる |
| 金銭的ロスの防止 | ・申請が遅れることで事後重症請求の場合に生じるもらい損ねを回避できる ・遡求請求可能な場合も迅速な手続きで最大限の受給を確保 |
障害年金専門の社労士のサポートを受けることで、複雑な手続きの負担を軽減し、精神的・時間的な余裕を得られます。
申請代行のメリットについては下記の関連記事でさらに詳しく解説しています。
 障害年金の申請代行を社労士に依頼する4つのメリット
障害年金の申請代行を社労士に依頼する4つのメリット
なお、表中に記載のあった「必要書類」や「事後重症請求」については、関連記事でご紹介しています。
 障害年金請求の必要書類は?提出先やよくある質問もまとめて解説
障害年金請求の必要書類は?提出先やよくある質問もまとめて解説
 事後重症請求とは【請求時の注意点までを解説します】
事後重症請求とは【請求時の注意点までを解説します】
まとめ
障害年金はご自分でも請求ができるものの、申請が複雑なため、正確な知識がないと等級が低く認定されたり、却下や不支給となってしまう可能性があります。
審査結果に納得ができない場合、不服申立てを行うことができますが、一般的に一度下された認定を覆すことはとても難しいです。
障害年金の申請がご自身で不安な場合は、早めに障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。