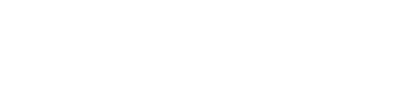脳出血は、脳内で出血が起こって血腫ができ、脳細胞を破壊する病気です。
脳出血を発症後はすぐに専門の医療機関を受診することが重要ですが、「一体どんな症状が脳出血の兆候なの?」と思う人も多いでしょう。
そこで、この記事では脳出血の兆候についてお伝えしていきます。
脳出血の種類別の兆候や、脳出血で後遺症が残ったときに申請できる可能性のある障害年金についてもご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
目次
脳出血とはどんな病気?
脳出血は、脳内の血管が破れて出血を起こす病気です。
脳出血は、脳梗塞やくも膜下出血と並ぶ「脳卒中」のひとつで、令和5年(2023年)には約10万5,000人が脳卒中で命を落としています。
脳出血の主な原因は高血圧で、動脈硬化で血管がもろくなり、血管が破れて出血が起こります。
脳の血管が破れて出血すると、「血腫」という血のかたまりをつくり、血腫のできた部分の脳細胞が破壊されるのです。
血腫で脳が圧迫されると脳の機能が低下し、さまざまな症状が現れます。
さらに、脳ヘルニアを起こし、生命にかかわる事態になる可能性があるので、早急に専門の医療機関へ受診することが大切です。
参考:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況(10ページ)|厚生労働省
脳出血の種類
脳出血は、出血部位によって以下のように分類されます。
順番にみていきましょう。
被殻出血
被殻出血は、大脳の奥にある「基底核」で出血する脳出血のひとつです。
主な症状として、片側の手足が動かしにくい、しびれる、話しにくいといった症状が出現します。
出血の大きさによって症状の程度は異なりますが、運動機能や言語機能に障害が生じやすいという特徴があります。
視床出血
視床出血は、感覚をつかさどる「視床」で起こる脳出血です。
主な症状として、手足のしびれや痛み、視野が欠けるなどの感覚障害があります。
また、意識障害や半身麻痺、言語障害なども現れることがあります。
小脳出血
小脳出血は、体のバランスをとる「小脳」で発生する脳出血です。
主な症状として、めまい、ふらつき、吐き気、まっすぐ歩けないといった平衡機能の障害が現れます。
また、頭痛や嘔吐、意識障害を伴うこともあります。
小脳は脳幹に近いため、出血が大きくなると生命に関わる危険性があり、早急な治療が必要です。
脳幹出血(橋出血)
脳幹出血(橋出血)は、生命維持に関わる「脳幹」で発生する最も重篤な脳出血の一つです。
主な症状として、意識がなくなる、呼吸が苦しくなる、手足が動かないなどの重症な症状が突然出現します。
また、瞳孔異常や言語障害、嚥下障害なども伴うことが多く、生命に直接関わる危険性が高いため、緊急の治療が必要です。
皮質下出血(脳葉出血)
皮質下出血(脳葉出血)は、大脳の表面近くで発生する脳出血です。
主な症状として、けいれん、言葉が出にくい、性格の変化といった症状が出現します。
出血部位によって症状は異なり、視覚障害や記憶障害、判断力の低下なども見られることがあります。
なお、脳出血の原因による分類もあります。
- 特発性脳出血
高血圧や脳動脈硬化が主な原因 - 症候性脳出血
動脈瘤、動静脈奇形、腫瘍、外傷などが原因
この記事では、脳出血の出血部位による兆候を中心にお伝えします。
脳出血の種類別!出やすい兆候一覧
脳出血の種類と兆候を表にまとめました。
| 脳出血の種類 | 特徴 | 主な兆候 |
|---|---|---|
| 被殻出血 | ・大脳の被殻が損傷 ・脳出血の中で最も多い | ・片側の手足の麻痺 ・ろれつが回らない ・意識障害 |
| 視床出血 | ・視床が損傷 ・脳出血の中で2番目に多い | ・片側の感覚異常 ・手足のしびれ ・意識障害 ・視野障害 |
| 脳幹出血(橋出血) | ・脳幹に出血が起こる ・重篤化しやすい | ・突然の意識障害 ・呼吸障害 ・瞳孔の異常 ・四肢麻痺 |
| 小脳出血 | ・小脳が損傷し、バランス感覚が失われる | ・めまい ・ふらつき ・嘔吐 ・歩行困難 ・頭痛 |
| 皮質下出血 | ・大脳皮質の下に出血が発生 | ・けいれん ・認知機能の低下 ・片側の運動麻痺 |
上記のような兆候が現れた場合は、脳出血の可能性があるので早急な対応が必要です。
特に片側の麻痺、言語障害、意識の混濁などの症状が出たら、すぐに医療機関を受診しましょう。
脳出血の兆候セルフチェック!
脳出血の兆候は多岐に渡るので、「これは脳出血なのか、それともほかの病気なのか」と迷うことも多いでしょう。
脳出血の治療は時間との戦いです。
少しでも早く医療機関へとつなぐために、次のポイントをセルフチェックして、脳出血の早期発見にお役立てください。
症状で見るチェックポイント
症状別に確認するポイントをまとめました。
| 症状 | チェックポイント |
|---|---|
| 突然の激しい頭痛 | これまでに経験したことのない激しい頭痛が発生していないか |
| 吐き気・嘔吐 | 頭痛とともに吐き気や嘔吐がないか |
| 運動障害 | 手足の麻痺や動かしにくさ、歩行の困難さがないか |
| 顔の症状 | 顔の片側に麻痺や動かしにくさ、表情の左右差がないか |
| 言語の問題 | 言葉が不明筭になっていないか |
| 視覚の変化 | 視界のぼやけや二重視などの視覚障害がないか |
| 言語の問題 | 言葉が不明瞭になっていないか |
脳出血は、適切な治療を早く受ければ、後遺症を軽くすることができます。
表内のような症状があるときは、すぐに専門の医療機関を受診しましょう。
ACT FASTを活用しよう!
アメリカの脳卒中協会が作成した「ACT FAST」という脳卒中の簡易チェックがあり、脳卒中の早期発見にも役立ちます。
| 試すこと | 脳卒中の可能性があるとき | |
|---|---|---|
| Face(顔) | 口を横にひいて笑う | ・口を横にひくと、口がゆがむ ・顔が片側だけ下がる ・口角が下がる |
| Arm(腕) | 手のひらを上にして、両手を前に上げる | ・片方の手が下がる |
| Speech(言葉) | 簡単な文章を言う | ・言葉が出てこない ・呂律が回らない ・言葉が理解できない |
| Time(時間) | 発生時刻を確認して | |
| Act (行動) | すぐに救急車を呼ぶか医療機関を受診しよう |
上記のような症状が出たら、すぐに救急車を呼んだり、専門の医療機関を受診したりすることが大切です。
参考:くまもと県脳卒中ノート(熊本大学病院 脳卒中・心臓病等総合支援センター)
脳出血にならないためにできること
脳出血は突然起こりますが、生活習慣を整えることで予防ができる病気です。
脳出血を予防するために、以下の方法を実践しましょう。
順番にみていきましょう
(1)血圧管理
脳出血を予防するためには、血圧管理が最も重要です。
定期的に血圧を測定し記録をつけることで、自身の血圧の傾向を把握することができます。
血圧を毎日測定することで、ちょっとした体調の変化にも気づけるため、早期に対応ができる点が大きなメリットです。
もし、高血圧だと診断されたら、医師の指示に従って適切に治療を受けることが大切です。
服薬治療が必要な場合は、確実に薬を飲みましょう。
また、定期的な通院で血圧の変動をチェックし、必要に応じて治療内容の調整を行うことも重要です。
(2)生活習慣の改善
脳出血の予防には、生活習慣の改善が重要な役割を果たします。
まず、塩分の過剰摂取を避け、減塩を心がけることが大切です。
1日の塩分摂取量を適切に管理することで、血圧上昇を防ぐことができます。
また、週に数回の適度な運動を行うことで、血圧低下効果が期待できます。
ウォーキングなどの有酸素運動や、ヨガやストレッチなどできる範囲で続けましょう。
喫煙は脳出血のリスクを高めるため、禁煙することをおすすめします。
さらに、過度のアルコール摂取は血圧上昇を招くため、節酒を心がけることも重要です。
これらの生活習慣改善を継続的に実施することで、脳出血予防に効果が期待できます。
(3)食生活の改善
脳出血の予防には、バランスの取れた食生活が重要です。
野菜や果物を多く摂取することで、体に必要なビタミンやミネラル、食物繊維を補給することができます。
特に、ほうれん草やブロッコリー、納豆などのカリウムを多く含む食材は血圧低下に効果があるとされています。
また、脂肪の摂取を控えることで、肥満予防や血管の健康維持につながります。
特に、動物性脂肪は控えめにし、魚油などの良質な脂肪を適度に摂取するといいでしょう。
上記のように食生活を改善して、継続的に実践することが大切です。
(4)ストレス管理
脳出血の予防には、休養とストレス管理が重要な要素となります。
ストレスをためることなく暮らせるのが理想的ですが、現代社会ではそれが難しいのが現状です。
特に働き盛りで休日も忙しい場合は、1日のなかでリラックスする時間を意識的に作り、ストレスを発散することが大切です。
例えば、入浴時にゆっくり過ごす、軽い運動をする、趣味の時間を持つなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが効果的です。
適度に休養をとり、心身のバランスを保つよう心がけましょう。
(5)定期的な健康診断
健康診断を定期的に受けることで、脳出血のリスクを減らせます。
脳出血の主な原因である高血圧は自覚症状がないので、健康診断で見つかることが多いです。
また、健康診断を受ければ、脳血管予防だけではなく、心房細動や不整脈など疾患や二次性高血圧の可能性を早期に発見することも期待できます。
自分の健康を再確認するためにも、定期的な健康診断はとても重要だといえます。
(6)睡眠の質の向上
十分な睡眠時間を確保し、睡眠の質を上げることは、脳出血の予防につながります。
脳出血の原因となる高血圧は、肥満や加齢などさまざまな原因で起こりますが、睡眠不足でも引き起こされます。
忙しい現代社会では、「なかなか睡眠時間を確保できない」という人も多いですが、まず1週間だけ睡眠時間を確保する生活を送ってみてはいかがでしょうか。
わずか1週間でも、ふだんの睡眠不足が解消されて心身ともに健やかになったと実感できる人が多いでしょう。
睡眠を見直すと脳出血予防だけでなく、仕事や勉強にもしっかり取り組めるようになるなど、あなたの生活が一変する可能性があります。
ご紹介した6つの予防法を日常生活に取り入れることで、脳出血のリスクを低減することができます。
脳出血の予防には高血圧管理が最も重要です。
生活習慣の改善と適切な医療管理を組み合わせることをおすすめします。
脳出血で後遺症が残ったら
脳出血で後遺症が残った場合、障害年金を申請できる可能性があります。
障害年金は、現役世代の人が病気やけがで障害を負い、生活や仕事に支障がある場合に申請できる制度です。
障害年金は、どのくらい障害により生活等に制限や支障があるかで年金額が決まるので、「脳出血だから」という理由で年金額が増減することはありません。
令和6年度の障害年金の年金額は以下のとおりです。
| 障害の程度 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625円 ※子の加算額あり | 報酬比例の年金額×1.25 ※配偶者の加算あり |
| 2級 | 831,700円 ※子の加算額あり | 報酬比例の年金額 ※配偶者の加算あり |
| 3級 | なし | 報酬比例の年金額 ※最低保証額623,800円 |
| 障害手当金 | なし | 報酬比例の年金額×2 ※支給は一度のみ |
報酬比例の年金額は、年金加入期間が長く、高い給与を受けていた人ほど年金額が多くなります。
誕生月に届く「ねんきん定期便」でおおよその年金額がわかるので、参考にしてみてください。

脳出血での障害年金申請でお困りのときは、ピオニー社会保険労務士事務所がお力添えできます。
お気軽にお問合せください。
障害年金制度の詳細や脳出血での障害年金受給については、関連記事でわかりやすくご紹介しています。
 脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
 障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
まとめ
脳出血は、脳内で出血が起こり血腫ができ、脳細胞を破壊する病気です。
脳出血を含む脳卒中は、日本人の死亡原因第4位で2023年には約10万人強が脳卒中で命を落としています。
脳出血の兆候は、激しい頭痛や手足の麻痺などがあり、発症した部位により兆候が変わります。
脳出血を発症した後はすぐに救急車を呼んだり、専門の医療機関を受診することが大切です。
また、脳出血で障害が残った場合は、障害年金を申請できることがあります。
脳出血の後遺症で辛いときに障害年金を申請するのは、大変なケースが多いようです。
もし、自分や家族で障害年金の申請ができないと感じたら、障害年金専門の社労士へ相談することをおすすめします。