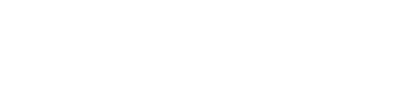2019年4月の法改正により、障害者手帳のカード化が始まりました。従来の紙の手帳に加え、希望する方はカード形式での交付が受けられます。
本記事では、障害者手帳のカード化について、メリット・デメリット、障害者手帳の対象疾患などについて解説します。
障害者手帳の交付要件もわかりやすくご紹介するので、障害者手帳の申請やカード型への切り替えを検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
障害者手帳のカード化とは
障害者手帳のカード化とは、従来の紙の手帳に代わり、プラスチック製のカード型の障害者手帳を交付する制度です。
これまでは、療育手帳のみカード化が認められていました。
2019年4月の法改正により、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳もカード化ができるようになり、現在は多くの自治体で導入されています。
障害者手帳のカード化は義務ではなく、当事者のニーズを踏まえて紙製かカード型の手帳のどちらかを選ぶことができます。
本人や家族が希望すれば、これまで通り紙製の手帳を継続して使い続けることも可能です。
これから障害者手帳を申請する人は、申請時に従来の手帳型かカード型かを選択します。
すでに障害者手帳を持っている人については、再交付の際に従来の手帳かカード型を選択する手続きを取る自治体と、本人の希望でカード型に切り替える自治体があります。
どちらの方式を採用しているかは、お住まいの市区町村役所にお尋ねください。
カード型の障害者手帳のイメージは次のとおりです。
【身体障害者手帳】
.png)
.png)
【精神障害者保健福祉手帳】
.png)
.png)
カードには、氏名、顔写真、手帳の種類・等級、有効期限などが記載されています。
障害者手帳のカード化を導入している主な自治体
障害者手帳のカード化の導入については、自治体の判断に任せられているため、カードタイプを交付していない自治体もあります。
障害者手帳のカード化を導入している主な自治体は、以下のようなところです。
- 東京都
- 神奈川県
- 佐賀県
- 神奈川県横浜市
- 神奈川県川崎市
- 神奈川県相模原市
- 宮城県仙台市
- 大阪府箕面市 など
今後の導入に向けて、検討や準備をしている自治体もあります。
「現在、カードタイプの手帳を交付しているか」「カード型の交付導入予定があるか」については、お住まいの市区町村役所へご確認ください。
障害者手帳のカード化のメリット
障害者手帳をカード化するメリットは、次の3つが挙げられます。
- 破損しにくい
- 持ち運びが便利
- 提示しやすい
カードタイプの障害者手帳はプラスチック製で、従来の手帳よりも水濡れによる破損に強く、耐久性に優れていることが大きな特長のひとつです。
カード型の手帳は、保険証や免許証と同じサイズで、財布やカードケースに入れて携帯することができます。
従来の手帳よりも持ち運びやすい点もメリットといえるでしょう。
公共施設等での割引の際に提示するときにも、カードタイプであれば手帳を開く手間がなく、さっと取り出せるので使い勝手が良くなります。
障害者手帳のカード化のデメリット
メリットの多い障害者手帳のカード化ですが、デメリットとしては次の3つが挙げられます。
- 文字が小さい
- 追加表記ができない
- 住所が表面に記載されている
カード型の障害者手帳は、「文字が小さくて見づらい」「スペースが小さいため書き込める情報が少ない」といったことがあります。
カード型の手帳の表面は追加記載ができないため、氏名や保護者の変更の場合は、手帳が再交付になります。
また、住所がカードの表面に記載されるので、個人情報が人の目につきやすく、抵抗感を持つ人もいるでしょう。
こういった再交付の手間や個人情報保護の観点から、従来の手帳型を選択するケースもあります。
障害者手帳の種類と交付要件
ひとくちに「障害者手帳」といいますが、障害者手帳には次の3種類があります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
3種類の障害者手帳の違いを表にまとめました。
| 身体障害者手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 療育手帳 | |
|---|---|---|---|
| 交付主体 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・中核都市の市長 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・児童相談所を設置する中核都市の市長 |
| 等級 | 1級~6級 ※ 7級単独では手帳は交付されない | 1級~3級 | 重度(A) それ以外(B) ※ 自治体により更に区分されることもある |
| 所持者数 | 4,842,344人 | 1,345,468人 | 1,249,939人 |
次章で、それぞれの手帳を見ていきましょう。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体の機能に障害がある方に交付されます。
身体障害者手帳の対象となる疾患は、次のとおりです。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能の障害
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害
- ぼうこう・直腸機能障害
- 小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
- 肝臓の機能障害
身体障害者手帳の交付要件
身体障害者手帳を取得するためには、上記の対象の疾患があり、かつ一定以上その疾患が永続することが条件です。
1級から6級までの障害に身体障害者手帳が交付されますが、7級の障害単独では手帳は交付されません。
ただし、7級の障害が重複して6級以上となるような場合は手帳が交付されます。
身体障害者手帳をもっと知りたい人は、下記の関連記事をご覧ください。
 身体障害者手帳とは?等級・メリットについても解説
身体障害者手帳とは?等級・メリットについても解説
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象に交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、全ての精神障害です。代表的な精神疾患については、次のようなものがあります。
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる中毒精神病
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
精神障害者保健福祉手帳の交付要件
手帳の交付を受けるには、次の2つの条件を満たすことが求められます。
- 精神障害で初めて診察を受けてから6ヶ月以上経過している
- 精神障害のため、日常生活や就労に支援が必要とされる
手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日までとなり、2年ごとに認定を受けることが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の詳細は、関連記事でわかりやすくご紹介しています。興味のある方は、ぜひご覧ください。
 精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法まで徹底解説
精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法まで徹底解説
療育手帳とは
療育手帳とは、主に知的障害のある子どもに対して発行される手帳です。
子どもの頃に取得することが多いですが、大人になってからも取得することもできます。
例えば、「以前から知的障害症状があっても療育手帳を申請していなかった」「大人になってから知的障害があることが分かった」といった場合に、手続き可能です。
ただし、大人になってから病気や事故で知的機能に障害が出た場合は、療育手帳の対象外となります。
療育手帳の交付要件
療育手帳は、「児童相談所」または「知的障害者更生相談所」において知的障害があると判断された場合にのみ交付されます。
療育手帳は、交付を受けている方の年齢に応じて、以下のように障害の程度を見直す時期が定められています。
- 18歳未満の方はおおむね2年ごと
- 40歳未満の方は10年
なお、療育手帳は、取得基準や受けられるサービスの内容も各自治体によって異なります。
詳しい判断基準は、お住まいの自治体へご確認ください。
療育手帳については、下記の関連記事で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
 療育手帳とは?対象基準やメリットまで徹底解説
療育手帳とは?対象基準やメリットまで徹底解説
障害者手帳アプリでさらに快適に
ここまで、障害者手帳について見てきましたが、各自治体では新しい取り組みを始めているところがあるのでご紹介します。
情報のデジタル化への対応に合わせて「障害者手帳アプリ」が誕生し、多くの自治体で導入されるようになっています。
利用方法としては、ご自身のスマホのアプリに障害者手帳を登録します。
すると、手帳情報をスマホ画面に表示できるようになり、その画面を公共施設等で提示することで、障害者割引を受けられるものです。
さらに、障害者手帳アプリでは、飲食店やレジャー施設などでお得に使える電子クーポンを提供したり、生活に役立つ情報やお得な情報をひとりひとりに合わせて配信したりするなどのサービスを提供しています。
アプリの活用で、さらに障害者手帳が使いやすくなるでしょう。
障害者アプリが導入されているかは、お住まいの自治体のホームページや役所でご確認下さい。
障害者手帳の申請方法
一般的な障害者手帳の申請方法をみていきましょう。
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請方法
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は、以下の流れで申請を行います。
どちらの手帳も申請から発行まで約1〜2ヶ月かかります。
療育手帳の申請方法
療育手帳の一般的な申請の流れは以下のとおりです。
療育手帳の判定機関は申請者の年齢によって以下のようになります。
| 申請者の年齢 | 判定機関 |
|---|---|
| 18歳未満 | 児童相談所 |
| 18歳以上 | 知的障害者更生相談所 |
療育手帳の申請から発行までにかかる期間は、2ヶ月程度です。
障害者手帳の申請方法の詳細は、下記の関連記事でわかりやすく解説しています。
 障害者手帳とは【完全初心者向け】
障害者手帳とは【完全初心者向け】
まとめ
障害者手帳は、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。
2019年の法改正により、障害者手帳のカード化が認められました。
カードタイプの手帳はプラスチック製で耐久性に優れ、持ち運びが便利になったことが大きなメリットといえます。
ただし、自治体によって導入していない地域もあるため、カードタイプの手帳に切り替えたい人はお住まいの市区町村役所やホームページで事前に確認しましょう。