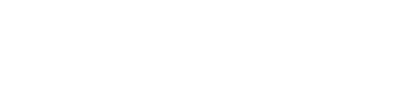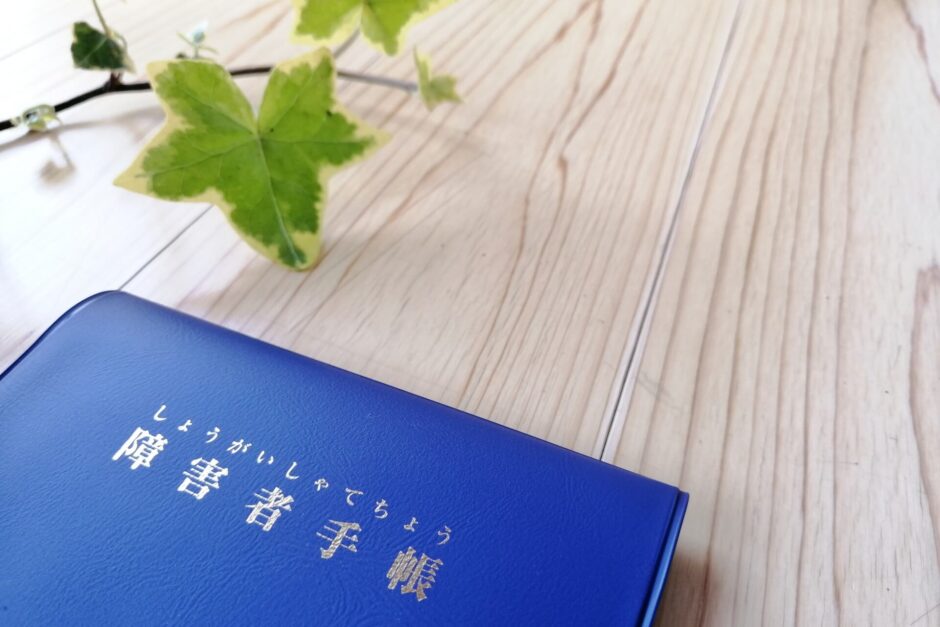障害者手帳は、障害のある方が社会生活を円滑に送るために、役立つ支援を受けられる制度です。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、それぞれ交付対象や等級基準などが異なります。
この記事では、障害者手帳の等級について以下を中心に、わかりやすく解説します。
- 障害者手帳の種類と等級とは
- 障害者手帳の交付対象
- 障害者手帳の申請方法
障害者手帳で受けられるサービスについてもご紹介するので、障害者手帳の申請を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
障害者手帳の交付対象は?どんな人がもらえる?
障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つの手帳を合わせた呼び方です。
障害者手帳は、心身に障害のある人が受けられるもので、生まれつきの知的障害のある人も交付対象です。
3種類の障害者手帳の違いを下表にまとめます。
(表1)障害者手帳の違いと交付対象疾患
| 身体障害者手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 療育手帳 | |
|---|---|---|---|
| 交付主体 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・中核都市の市長 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 | ・都道府県知事 ・指定都市の市長 ・児童相談所を設置する中核都市の市長 |
| 等級 | 1級~6級 ※ 7級単独では手帳は交付されない | 1級~3級 | 重度(A) それ以外(B) ※自治体により更に区分されることもある |
| 交付対象となる疾患 | ・視覚障害 ・聴覚・平衡機能の障害 ・音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 ・肢体不自由 ・心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害 ・ぼうこう・直腸機能障害 ・小腸の機能障害 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害 ・肝臓の機能障害 | ・統合失調症 ・うつ病、そううつ病などの気分障害 ・てんかん ・薬物やアルコールによる中毒精神病 ・高次脳機能障害 ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等) ・その他の精神疾患(ストレス関連障害等) などの全ての精神障害 | 知的障害 |
障害者手帳をもっと詳しく知りたい人は、関連記事でわかりやすくご紹介しています。ぜひご覧ください。
 障害者手帳とは【完全初心者向け】
障害者手帳とは【完全初心者向け】
次章では、それぞれの手帳の等級について解説していきます。
身体障害者手帳の等級と決め方
身体障害者手帳では、日常生活の支障の程度や症状の種類により、7つの障害等級に区分されています。
手帳が交付されるのは、6級以上の障害がある場合です。
7級にあたる障害単独では身体障害者手帳の交付対象とはなりません。
ただし、7級の障害が2つ以上ある場合や、7級のほかに6級以上の障害がある場合には手帳が交付されます。
また、身体障害者手帳の等級は、障害ごとに等級表によって細かく決められています。
下記は視覚障害の例と聴力障害の例です。
1級 視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下 かつ 他方の眼の視力が0.02以下のもの
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
6級 両耳の聴力レベルが70デジベル以上のものなど
詳しい障害程度やその他の障害等級については、厚生労働省の身体障害者障害程度等級表でご確認ください。
身体障害者手帳の交付要件
身体障害者手帳を取得するためには、前述の対象疾患(表1)があり、かつ一定以上でその疾患が永続することが条件
上記の「一定以上でその疾患が永続すること」とは、障害が将来にわたり回復する可能性が極めて低い状態であることを指します。
身体障害者手帳の有効期限はありません。
ただし、障害の状態が変わったり、障害がなくなった場合には「等級変更」や「返還」の手続きが必要です。
身体障害者手帳をもっとくわしく知りたい人は、以下の関連記事をご一読ください。
 身体障害者手帳とは?等級・メリットについても解説
身体障害者手帳とは?等級・メリットについても解説
精神障害者保健福祉手帳の等級と決め方
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活または社会制約がある人を対象に交付される手帳です。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、日常生活や社会生活における支障の程度により、1級から3級の「障害等級」に分けられます。
下表は障害等級ごとの大まかな基準です。
(表2)障害等級と生活上の支障の程度
| 障害等級 | 生活における支障の程度 |
|---|---|
| 1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 精神障害であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 精神障害であって、日常生活や社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
精神障害者保健福祉手帳の等級は、具体的には、「精神疾患の状態」と「能力障害の状態」という2つの基準で判断されます。
精神疾患の状態は診断名によって変わります。
一方で、能力障害の状態は「日常生活や仕事をする際にどんな困りごとがあるか」により判断される点が大きな特徴です。
例えば、1級の能力障害の状態では、「通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない」「家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない」などの基準が示されています。
障害等級の判定基準の詳細は、精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について|厚生労働省でご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳の交付要件
精神障害者保健福祉手帳の交付要件は、以下の2つです。
- 精神障害で初めて診察を受けてから6ヶ月以上経過している
- 精神障害のため、日常生活や就労に支援が必要とされる
手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日までです。
手帳の更新には、2年ごとの認定が必要ですので、忘れずに手続きしましょう。
精神障害者保健福祉手帳の詳細は、下記の関連記事でご紹介しています。
 精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法まで徹底解説
精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法まで徹底解説
療育手帳の等級と決め方
療育手帳は、知的機能の障害が発達期にあらわれ、日常生活に支障が生じ、援助を必要とする人に交付される手帳です。
厚生労働省の通知では、療育手帳の等級を重度(A)とそれ以外(B)に大きく2つに区分していますが、自治体によっては細分化しているところもあります。
下表に、自治体での区分例をまとめました。
| 自治体名 | 等級の区分 |
|---|---|
| 東京都 | 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度) |
| 大阪府 | A(重度)、B1(中度)、B2(軽度) |
| 名古屋市(愛知県) | 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度) |
| 北海道 | 軽度、中度、重度、最重度 手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分 |
なお、療育手帳は、都道府県・政令指定都市がそれぞれ判定基準や運用方法を定めて実施しているため、制度名や支援内容、取得基準などが異なる場合があります。
例えば、療育手帳という呼称は使用せず、東京では「愛の手帳」、青森や名古屋では「愛護手帳」といった名称で呼ばれています。
療育手帳の支援内容や取得基準の詳細は、お住まいの市区町村役所のホームページや担当窓口等にお尋ねください。
参考:判定について(愛の手帳Q&A)|東京都心身障害者福祉センター
参考:療育手帳について|大阪府
参考:愛護手帳|名古屋市
療育手帳の交付要件
療育手帳の交付要件は、以下のとおりです。
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された方に交付される
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受けます。
また、療育手帳は、交付を受けている方の年齢に応じて、以下のように障害の程度を見直す時期が定められています。
- 18歳未満の方はおおむね2年ごと
- 40歳未満の方は10年
自治体により、障害の程度の見直す時期が違うこともあるので、お住まいの市区町村役所で確認しましょう。
療育手帳は、下記の関連記事でさらに詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
 療育手帳とは?対象基準やメリットまで徹底解説
療育手帳とは?対象基準やメリットまで徹底解説
身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳の申請方法
身体障害者手帳と精神障害者福祉手帳の申請の流れは、次のとおりです。
※指定医とは、都道府県知事が指定した医師のこと
手帳の申請に必要な書類は、以下のようなものです。
- 申請書
- 診断書
- 本人確認ができる書類
- 申請する人の顔写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーがわかるもの
手帳の申請は本人や保護者の他、代理人による申請もできます。
代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
なお、申請から手帳の発行までは、約1〜2ヶ月かかります。
療育手帳の申請方法
療育手帳の申請の一般的な流れは、以下のとおりです。
申請書類や必要な手続きを確認
療育手帳の申請に必要な書類は、次のようなものです。
- 申請書
- 本人の確認書類
- 申請する人の顔写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーがわかるもの
申請から手帳が交付されるまでは、2〜4ヶ月程度かかります。
なお、療育手帳は、自治体により申請方法や必要書類が異なることがあります。
実際に申請する際は、お住まいの市区町村の障害者福祉窓口に確認してから手続きをしましょう。
障害者手帳で受けられるサービス
障害者手帳を取得すると受けられるサービスを、2つご紹介します。
経済的な支援が受けられる
障害者手帳を交付されると、税金の優遇や公共施設での割引などが受けられます。
主な助成や料金の割引を、以下にご紹介します。
- NHKの減免
- 所得税の控除
- 自動車税の軽減
- 美術館や博物館などの公共施設の割引
- 携帯電話料金の割引
- 鉄道やバスなど公共交通機関の割引
ただし、障害の種類や等級によって割引内容が異なることがあります。
具体的な割引サービスの内容については、ご利用になるサービスの運営会社のホームページで確認しましょう。
障害者手帳で受けられる割引は、下記の関連記事でさらに詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
 障害者手帳で受けられるお得な割引サービス7つ
障害者手帳で受けられるお得な割引サービス7つ
障害者雇用枠に応募できる
障害者手帳を交付されると、障害者雇用枠での求職に応募できます。
障害者雇用枠とは、障害のある人を対象として企業が求人を行い、雇用することです。
障害者雇用枠で採用されると、周囲から障害の特性や困りごとへの理解が得やすくなり、職場での配慮が受けやすくなります。
職場でのサポートを受けながら働けるため、職場に定着し長く勤められる可能性も高くなるといえるでしょう。
しかし、残念なことに障害者雇用枠での求人は一般の求人に比べると、求人数が少ない傾向があります。
障害者雇用枠での雇用を希望する場合、求人があったらすぐに応募できるように、普段から備えておくことも大切といえます。
障害者手帳の等級|よくある質問
障害者手帳の等級について寄せられる質問に回答していきます。
障害者手帳と障害年金の等級は、同じですか?
「障害者手帳」と「障害年金」はよく似た名称のため、混同されがちです。
しかし、それぞれ異なる制度のため、認定基準や等級分けも違います。
つまり、1級の障害者手帳に該当するからといって、1級の障害年金を受給できるわけではありません。
障害者手帳を取得したものの、障害年金は受給できるか不安に思っている方は、障害年金専門の社労士に相談してみましょう。

ピオニー社会保険労務士事務所では、障害年金の相談を受け付けています。
「障害年金を受けたいけれど、どうしたらいいかわからない」
「自分の状態で、障害年金はもらえるのかな」
こんな疑問や不安のある方は、弊所へぜひお問い合わせください。
障害者手帳の等級が変わることはありますか?
障害の状態が変わったときは、障害者手帳の等級が変わることがあります。
一般的な手続きは、以下のとおりです。
・身体障害の程度が変わったり、新たな障害が生じたときは、指定医に相談します。
・指定医が、「等級が変わる」と判断したら、診断書を作成してもらい、手帳の申請手続きをしましょう。
・精神障害の状態が変化し、障害等級が変わったと思う場合は、新規申請と同じ手続きをしましょう。
・障害の程度が変わったと思う場合は、再判定の申請をします。
いずれの手帳の場合でも、自治体により申請の手順が違うことがあります。
お手続きの際は、お住まいの市区町村の障害者福祉窓口にお問い合わせください。
参考:手帳を取ったときより、病状が重くなりました。手帳の内容を変更できますか|船橋市
まとめ
障害者手帳には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。
それぞれ等級や認定基準が異なり、手帳の種類によって申請方法も違います。
障害者手帳の申請を検討している方は、まずお住まいの市区町村の障害者福祉窓口に相談してみましょう。