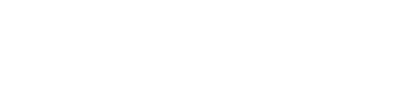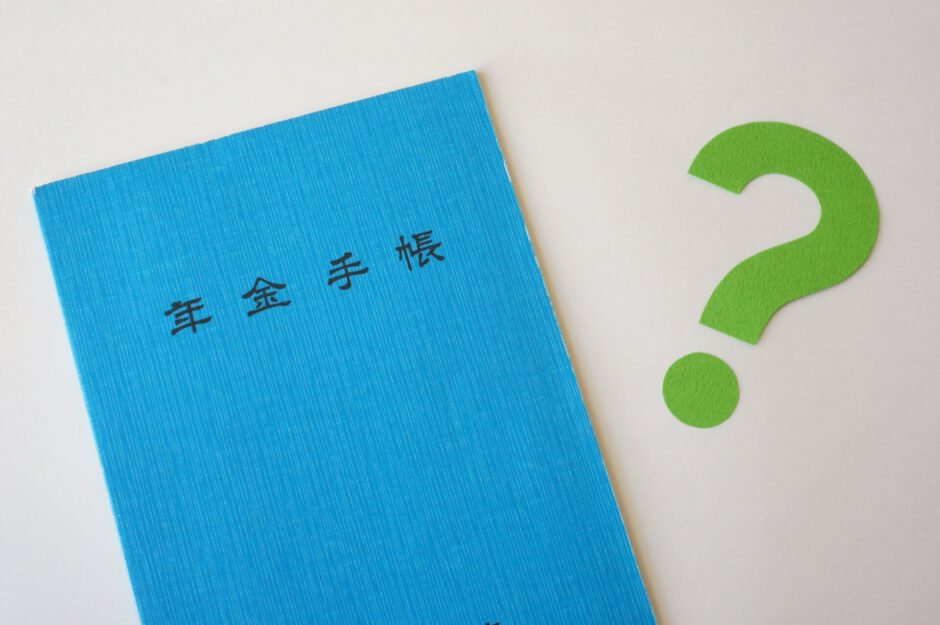2019年10月の消費税増税にともなって「年金生活者支援給付金」制度が始まりました。
年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入や所得が一定以下の年金受給者を対象に、通常の年金にプラスして支給される給付金です。
そこで今回は、年金生活者支援金の支給要件や支給額、申請方法などについて解説します。
これから年金を請求する方やすでに年金を請求している方で、年金生活支援給付金について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
年金生活者支援給付金とは?
年金生活支援給付金とは、所得が一定基準より低い年金受給者の生活を支援するために、通常の年金にプラスして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。
年金生活者支援給付金は、原則として給付金の請求をした翌月から支給が開始され、年金と同様に偶数月の支給日に2ヶ月分が一度に振り込まれます。
ただし、通常の年金は請求から遅れた場合でも5年分はさかのぼって支給されますが、年金生活者支援給付金はさかのぼって請求ができません。
そのため、年金生活者支援給付金の請求書が届いたら早めに手続きを行うようにしましょう。
年金生活者支援給付金の支給要件と対象者
先述したように、年金生活者支援給付金には3種類の給付金があり、それぞれ支給要件が異なります。
そこでここからは、それぞれの支給要件と対象者について解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金とは、現在老齢基礎年金を受給しており、かつ所得が一定以下の方に支給される給付金です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は次のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入額(※1)とその他の所得(給与所得や利子所得)の合計額が、881,200円以下(※2)である
※1:障害年金、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2:前年の年金収入額+その他の所得額の合計が、781,200円を超え881,200円以下である方には「補足的老齢年金生活支援給付金」が支給されます。
参考:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(日本年金機構)
障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害基礎年金の受給者で、次の2つの要件を満たしている方は、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
前年の所得については、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含みません。
また、所得の上限は扶養親族の数によって変動しますが、「38万円」という数字も誰が扶養親族かによって変わります。
- 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族基礎年金を受給しており、支給要件を満たしている方は、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は、次のとおりです。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
前年の所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
また、障害年金生活者支援給付金と同様に、38万円という数字も誰が扶養親族かによって変動します。
- 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
続いて、それぞれの年金生活者支援給付金の支給額について解説します。
老齢年金生活者支援給付金の給付額
老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と保険料免除期間によって変わります。
具体的には、次の①と②の合計金額が給付額となります。
①保険料納付済期間に基づく給付額(月額)=5,310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく給付額(月額)=11,333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
上記の5,310円の部分は、毎年物価によって見直されるため、年ごとに変動します。
また、11,333円の部分は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除の場合の金額で、保険料が4分の1免除の場合は、5,666円で計算します。
障害年金生活者支援給付金の給付額
障害年金生活者支援給付金の給付額は、障害等級ごとに異なります。
- 障害等級2級の方:5,310円(月額)
- 障害等級1級の方:6,638円(月額)
ただし、給付額は物価によって変動するため、毎年の見直しにより変わることがあります。
遺族年金生活者支援給付金の給付額
遺族年金生活者支援給付金の給付額は、月額5,310円です。
ただし、給付額については障害年金生活者支援給付金と同様に、物価変動によって毎年給付額が見直され、給付額が変わることがあります。
また、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれの子に対して支払われます。
年金生活者支援給付金の申請方法
障害年金生活支援給付金を受け取るためには、日本年金機構への請求手続きが必要です。
そこでここからは、すでに年金を受け取っている方と、これから年金を受け取る方の請求方法について確認しておきましょう。
すでに年金を受け取っている方
すでに年金を受給している方の場合、日本年金機構が毎年市町村から所得に関する情報を受け取り、受給条件を満たすかどうかが判定されます。
そして、前年よりも所得が低下したなどの理由で新たに支給対象となった方は、日本年金機構からハガキ形式の請求書が郵送されてきます。
請求書が郵送されたら、届いた請求書に必要事項を記入して、切手を貼って投函すれば請求の手続きは完了です。
これから年金請求をする方
これから年金を請求する方の場合、年金の請求手続きをするタイミングで、給付金の請求手続きも合わせて行います。
本人が請求書を記載することが難しい場合は、代理人などの代筆も可能です。
請求書が届いたら、上述したように必要事項を記入して投函すれば手続きは完了となります。
更新手続きは不要
障害年金生活者支援給付金の手続きは一度行えば、翌年以降の手続きは不要です。
もしも、年度の途中で年金生活者支援給付金の対象要件から外れてしまった場合は、特に手続きの必要はなく、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
なお、給付要件から外れて、年金生活者支援給付金の支給対象外となった場合は、その後再度給付要件を満たしたタイミングで改めて手続きが必要となります。
年金生活者支援給付金が支給停止となるケース
支給要件を満たしている限り、年金生活者支援給付金はずっと受給できますが、途中で支給停止となるケースもあります。
そこでここからは、年金生活者支援給付金が支給停止となるケースについて具体的に解説します。
受給者の年金支給が停止となったとき
年金生活者支援給付金は、あくまでも年金とそれ以外の収入を含めても、一定の水準以下にしかならない方を対象とした給付金です。
したがって、年金が支給停止となった場合は、年金生活者支援給付金も自動的に停止となります。
受給者の所得が超過したとき
年金がもらえる所得範囲で働いていても、年金生活者支援給付金が設定している支給要件の所得範囲を超えた場合、支給対象外となります。
ただし、この場合、所得が超過したときにすぐに支給停止となるのではく、対象年度が終了するまでは年金生活者支援給付金を受給することが可能です。
前年の所得が超過し、次年度の年金生活者支援給付金が支給されなくなる予定の受給者には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」のハガキが郵送されます。
受給者が亡くなったとき
年金生活者支援給付金の受給者が亡くなると、死亡時点で年金生活者支援給付金の受給権利はなくなります。
しかし、年金生活者支援給付金は2ヶ月に一度振り込まれるため、給付金の支払日前に受給権者が亡くなった場合、未払いの給付金が発生します。
この未払いとなった給付金については、受給者の遺族が請求して受け取ることが可能です。
請求できる遺族は、亡くなった受給者と生計を同じくしていた次の遺族です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等以内の親族(おじ、おば、甥、姪など)
遺族の優先順位は1.〜7.の順です。
また、未支払分の年金についても請求できる遺族は同様なので、請求をする人は年金と給付金を合わせて請求することになります。
なお、同順位の遺族が複数いる場合は、そのうち1人が代表者として請求します。
年金生活者支援給付金でよくある質問
最後に、年金生活者支援給付金を申請するにあたり、よくある質問についていくつかまとめたので、ご参考ください。
年金生活者支援給付金は課税対象ですか?
年金生活者支援給付金は、非課税となります。
特に、老齢基礎年金の場合、課税対象となるため老齢年金生活者支援給付金も課税対象となると誤解している方も少なくありません。
しかし、年金生活者支援給付金は対象にかかわらず、すべて非課税収入となります。
年金生活者支援給付金はいつまでもらえますか?
年金生活者支援給付金は恒久的な制度のため、支給要件を満たしている限り制度が続いている間は、継続して給付金を受け取れます。
ただし、支給要件から外れた場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給停止となります。
なお、支給停止となりその後再び支給要件を満たした場合は、再度手続きが必要です。
さいごに
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者のうち、所得が一定額以下の人の生活を支える給付金です。
支給要件や支給額は受給している年金の種類によって変わり、障害年金の場合は、障害基礎年金の受給者の方で、所得が一定額以下であれば支給対象となります。
また、請求手続きをした翌月から支給開始となるため、給付要件に該当する方は早めに手続きを済ませてしまいましょう。