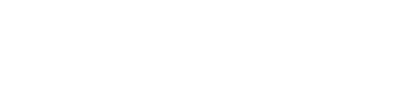精神疾患でも障害年金が受給できる可能性があることをご存じですか?
障害年金は「身体障害ではないから、もらえない」と思われがちですが、うつ病や発達障害、高次脳機能障害などの精神疾患で障害年金を受け取っている人は多くいます。
この記事では、障害年金の支給対象となる精神疾患の病名や申請のポイントを障害年金専門の社労士がわかりやすくご紹介します。
あなたやご家族が精神疾患での障害年金申請に不安のある人や障害年金について疑問のある人はぜひ最後まで読んで参考にしてください。
目次
精神疾患でも障害年金が受給できる理由
精神疾患でも障害年金を受給できる大きな理由は、障害年金には「障害のある人の生活保障の役割」があるからです。
障害年金は病気やけがによって日常生活や仕事に著しい支障が出ている人を支える公的年金制度です。
厚生労働省が定める障害等級(1級~3級)の基準を満たせば、精神疾患でも障害年金が受け取れます。
つまり、精神疾患によって、これまで当たり前にできていた家事や外出、仕事といった活動が困難になったり、継続することが著しく難しくなったりするなら、障害年金の対象となり得るのです。
精神疾患による困難は目に見えにくいですが、その人が抱える生きづらさは身体的な障害と何ら変わりません。
そのため、精神疾患のある人を経済的に支える制度として障害年金が用意されています。
なお、障害年金の詳細は関連記事でご紹介しています。
 障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
障害年金とは【専門家がわかりやすく解説します】
障害年金は「請求」するものですが、この記事では一般的に浸透している表現を採用して「申請」と表記します。
障害年金がもらえる精神疾患の病名は?
障害年金の支給対象となる主な精神疾患の病名は次のようなものが挙げられます。
- 統合失調症
- 妄想性障害
- 統合失調感情障害
- うつ病
- 双極性感情障害(躁うつ病)
- 反復性うつ病性障害
- 気分変調症
- 高次脳機能障害
- アルツハイマー病の認知症
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、ADHDなど)
- トゥレット症候群 など
上記のように障害年金は多くの精神疾患を支給対象としていることがわかります。
障害年金の対象にならない精神疾患とは?
精神の障害であっても、人格障害や神経症は障害年金の認定対象とはなりません。
【障害年金の対象とはならない精神疾患】
| 神経症 | ・不安神経症 ・広場恐怖症 ・社会恐怖症 ・パニック障害 ・強迫性障害 ・適応障害 ・急性ストレス反応 ・外傷後ストレス障害(PTSD) ・解離性障害・身体表現性障害 など |
| 人格障害 | ・パーソナリティ障害 ・性同一性障害 など |
ただし、神経症は「精神病の病態を示しているものについては統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う」とされています。

神経症と診断されていても障害年金を受給できるケースもあります。
精神疾患でもらえる障害年金の金額は?
令和7年度の年金額は以下のとおりです。
| 障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625 円※子の加算額あり | 報酬比例の年金額×1.25※配偶者の加算あり |
| 2級 | 831,700 円※子の加算額あり | 報酬比例の年金額※配偶者の加算あり |
| 3級 | なし | 報酬比例の年金額※最低保証額623,800円 |
| 障害手当金 | なし | 報酬比例の年金額×2※支給は一度のみ |
なお、障害年金は、障害によりどのくらい生活や仕事に支障が出ているかにより等級が決定し、年金額が変わります。
「精神疾患だから」という理由で年金額が増減することはありません。
障害年金の金額をもっと詳しく知りたい人は下記の関連記事をご覧ください。
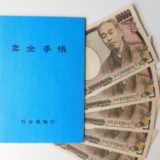 【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について
【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について
精神疾患で障害年金がもらえる程度とは
精神疾患がどのような程度であれば障害年金が受給できるかどうかを定めた大まかな基準は次のとおりです。
| 障害等級 | 基準 |
|---|---|
| 1級 | 常に誰かの援助がないと日常生活を送ることができない程度 |
| 2級 | 必ずしも誰かの援助を受ける必要はないが日常生活に支障がある状態 |
| 3級 | 労働に支障がある状態 |
障害年金では、疾病ごとに定めた「障害認定基準」が定められ、基準に沿って障害等級が決まります。
精神疾患別の障害認定基準については、下記に関連記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
▶統合失調症で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
▶うつ病での障害年金は難しい?受給するためのポイントと障害認定基準
精神疾患で障害年金を申請する流れ
精神疾患で障害年金を申請するときのおおまかな流れは次のとおりです。
- 初診日の確認
- 受診状況等証明書や診断書の取得
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 戸籍謄本などの提出書類の収集および請求書等の作成
- 年金事務所等へ提出
精神疾患の場合、一度の受診で診断名がつかず、何度も通院したり、転院を繰り返したりすることも多いです。
そのため、「初診日がいつなのかわからない」といったケースが多く見られます。

初診日がわからなかったり、病歴・就労状況等申立書などの作成が難しいと感じたりするときは、障害年金専門の社労士へ相談することをおすすめします。
以下の関連記事では、障害年金の申請を具体的にご説明しています。ぜひご覧ください。
 障害年金申請の流れとは?7つのステップで徹底解説
障害年金申請の流れとは?7つのステップで徹底解説
精神疾患で障害年金を申請するときのアドバイス
精神疾患で障害年金をもらうための準備をする上で、知っておくと役立つアドバイスは、次の3つです。
- 初診日の前から現在までの病歴を古い順から思い出して整理する
- 診断書を医師に依頼する時に簡単なメモを用意する
- 診断書の精神疾患の病名をしっかりと確認する
知っているのと知らないのでは、結果が大きく変わることがあります。
順番に見ていきましょう。
初診日の前から現在までの病歴を古い順から思い出して整理する
まずは、精神疾患を発症したとき(知的障害と発達障害の方は生まれた日)から今までのことをじっくりと整理してみましょう。
障害年金の申請をするために、年金事務所に相談をすると「初診日に行った病院で受診状況等証明書を取ってください」「障害認定日と今の病院で診断書を書いてもらってください」と説明されます。
そのため、真っ先に病院に行き、受診状況等証明書や診断書をすぐに作成依頼してしまう方がとても多いです。
しかし、病院に行く前に次のようなことを思い出し、これまでの病歴を整理しておくことをおすすめします。
- どんな症状が最初は出てきたのか。
- その症状で病院に行こうと思ったのはどうしてか。
- その病院を選んだのはどういう理由だったのか。
- 病院に行かなかった期間は、何をしていたのか。なぜ病院に行かなかったのか。
- 病院を変えた理由はどういうことだったのか。
- 病院ではどんな治療を受けて、どの位の頻度で通院し、治療開始後は症状に変化はあったのか。
- 働いていたのか。働いていたら、その時の症状はどうだったのか。
- 働いていない場合、どんな症状があって働くことができなかったのか。
上記のようなことを意識しながら思い出し、情報が揃ってきたらもっと具体的に、〇年〇月〇日~〇年〇月〇日は〇〇病院と、病院ごとに当てはめていきます。
この作業をすることにより、ご自分の精神疾患の症状や日常生活や労働の支障を正しく理解することができ、医師にも伝えやすくなります。
また、社労士に障害年金サポートを依頼する場合にも社労士に理解してもらいやすくなります。
診断書を医師に依頼する時に簡単なメモを用意する
診断書を医師に依頼するときには、伝えたいことをまとめたメモを作りましょう。
精神疾患で病院を受診する場合、診察は短時間で終わることが多いです。
例えばうつ病のある人でしたら、「眠れません。不安感が強いです。」というように症状のみを医師に訴えて、日常生活について伝えることまではしないケースが多く見られます。
そうすると、診断書に記載する肝心な「日常生活能力」について正しく記載してもらえない状態で診断書が作成されてしまうのです。
医師とはふだんの診察時から、生活や仕事での困りごとはどんなことかを共有しておくのが理想的ですが、うまく伝えられない人がほとんどです。
そこで、医師に診断書を依頼するときには、あらかじめ伝えたいことをメモしておくことをおすすめします。
診察室に入って緊張して話せないときは、用意しておいたメモを手渡すこともできるので、心強いアイテムとして準備しておきましょう。
診断書の精神疾患の病名をしっかりと確認する
診断書が出来上がったら、診断書の表面の①障害の原因となった傷病名を確認してください。
-1024x642.png)
ここに記載されている傷病名が、障害年金対象外の神経症や人格障害の傷病名になっていませんか?
もし、障害年金対象外の病名が記載されていると、それだけで障害年金が受給できない可能性があります。
また、ICD-10コードという欄がありますが、F10台、F40~60台になっていると障害年金対象外の病名ですので注意が必要です。
なお、ICD-10コードの詳細は、厚生労働省が公開しているICD-10コード(国際疾病分類)第5章 精神および行動の障害でご確認ください。
精神疾患で障害年金を受給後に更新はある?
精神疾患で障害年金を受給した場合、多くのケースで更新が必要です。
一度障害年金の支給が決定しても、「有期認定」の場合は永続的に年金支給が続くわけではありません。
精神疾患の場合、症状の改善や悪化が考えられるため、ほとんどのケースで「有期認定」が適用され、1年から5年の間で受給期間が定められます。
この更新手続きは、現在もなお障害年金の支給対象となる状態であるかを定期的に確認するための重要なプロセスです。
具体的には、定められた更新時期(誕生月の末日)までに、現在の障害の状態を記した医師の診断書を提出する必要があります。
診断書の内容に基づいて、引き続き障害等級に該当するかどうかが審査されます。
もし症状が改善し、日常生活や仕事への支障が軽くなっていると判断されれば、年金が停止されたり、等級が変更されたりする可能性もあります。
なお、障害年金の更新については、下記の関連記事でわかりやすくご紹介しています。
 【最新】障害年金受給後の更新(障害状態確認届)
【最新】障害年金受給後の更新(障害状態確認届)
障害年金の複雑な手続きは社労士へ相談を
精神疾患で障害年金の申請を検討されているなら、複雑な手続きは社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。
障害年金の申請プロセスは、多岐にわたる書類の準備や、専門的な知識が必要となる場面が少なくありません。
特に、精神疾患のある人はご自身の症状を正確に伝えたり、必要な書類を漏れなく揃えたりすることが大きな負担となるケースも多いでしょう。
社労士に申請を代行してもらえば、年金事務所に何度も足を運んだり、慣れない専門用語で書かれた書類に頭を悩ませたりする手間から解放されます。
ご自身やご家族だけで障害年金の申請を進めるのが難しいと感じたら、ぜひ専門家である社労士への相談を検討してみてください。
社労士に依頼するメリットについては、関連記事でわかりやすくご紹介しています。
 障害年金の申請代行を社労士に依頼する4つのメリット
障害年金の申請代行を社労士に依頼する4つのメリット
まとめ
精神疾患からくる症状で生活や仕事に支障がある場合、障害年金がもらえる可能性があります。
障害年金は、現役世代の人が病気やけがで障害を負い、生活や仕事に支障があるときに申請できる公的年金です。
身体障害だけではなく、うつ病などの精神疾患も障害年金の支給対象です。
障害年金の申請は複雑で自分や家族だけでは申請できないケースも多く見られます。
「書類の作成ができない」「何から始めるのかわからない」など障害年金でお困りのときはお気軽にピオニー社会保険労務士事務所にご相談ください。
経験豊富な社労士があなたの障害年金申請をサポートします。