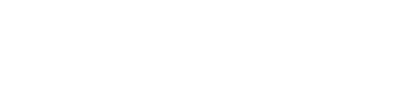「脳出血」と「脳梗塞」について、正確な違いがわかる人はあまり多くないようです。
どちらも「脳卒中」という大きな枠組みに含まれる病気ですが、その原因も特徴も大きく異なります。
このブログ記事では、脳出血と脳梗塞それぞれの特徴と違いをわかりやすく解説します。
また、後遺症が残った場合に生活を支える「障害年金」についても触れ、社労士がどのようにサポートできるかをお伝えします。
脳出血と脳梗塞の違いを知りたい人や、後遺症で申請できる障害年金について知りたい人は、ぜひ最後まで読んでお役立てください。
目次
脳出血と脳梗塞とは?それぞれの特徴と違い
脳出血と脳梗塞の違いを一言で表現するなら、脳出血は脳の血管が「破れる」ことで起こり、脳梗塞は脳の血管が「詰まる」ことで発生することです。
脳出血と脳梗塞は、どちらも脳の血管に問題が起こる「脳卒中」と呼ばれる病気ですが、その根本的な原因に大きな違いがあります。
発症メカニズムの違いが、症状の現れ方や治療法、さらには予後にも影響を及ぼすため、それぞれの特徴を理解しておくことがとても重要です。
脳出血とは
脳出血は、脳の血管が破裂し、脳の組織内に血液が流れ出すことによって起こる病気です。
流れ出た血液が脳組織を圧迫したり、破壊したりすることで、さまざまな症状が表れます。
高血圧が最も一般的な原因として知られており、その他にも動脈硬化や脳動脈瘤の破裂などが挙げられます。
脳出血の主な症状は次のとおりです。
- 突然の激しい頭痛
- 意識障害
- 手足の麻痺やしびれ
- 言葉がうまく話せない など
特に、高齢者や高血圧の持病がある方は、脳出血のリスクが高いとされており、出血した場所や出血量によって、重症度が大きく異なります。
脳出血の症状については関連記事をご覧ください。
 脳出血の症状と危険なサインとは?もしものときの障害年金サポート
脳出血の症状と危険なサインとは?もしものときの障害年金サポート
脳梗塞とは
脳梗塞は、脳の血管が血栓(血の塊)などによって詰まり、その先の脳組織に血液が供給されなくなることで、脳細胞が壊死してしまう病気です。
血液の流れが途絶えることで、酸素や栄養が届かなくなり、脳機能が損なわれます。
脳梗塞の原因はさまざまで、動脈硬化によって血管が狭くなる場合や、心臓でできた血栓が脳に飛んでくる場合(心原性脳塞栓症)などがあります。
脳梗塞の主な症状は次のとおりです。
- 手足の力が入らない
- ろれつが回らない
- 視野が欠ける
- 記憶障害や判断力の低下 など
脳梗塞の症状は脳出血に比べて軽く見えることもありますが、後遺症が残るケースも多いです。
時間とともに症状が進行することもあり、早期発見・早期治療が重要となります。
脳梗塞の症状や原因については、関連記事でさらに詳しくご紹介しています。
 脳梗塞とは?前兆から後遺症、障害年金まで徹底解説
脳梗塞とは?前兆から後遺症、障害年金まで徹底解説
 脳梗塞の原因とは?ストレスや食事との関係性も解説
脳梗塞の原因とは?ストレスや食事との関係性も解説
脳出血と脳梗塞の主な違い一覧
脳出血と脳梗塞の主な違いを表にまとめました。
| 脳出血 | 脳梗塞 | |
|---|---|---|
| 原因 | 脳血管の破裂 | 血管の詰まり |
| 発症の速さ | 突然 | 比較的ゆっくり |
| 主な原因 | 高血圧 動脈硬化 脳動脈瘤の破裂 | 動脈硬化、心房細動などの心疾患 |
| 後遺症 | 重度になる傾向 | さまざまな症状が残る傾向 比較的軽度な例もあり |
脳出血と脳梗塞はどちらが重症?
初期の重症度や発症後の致死率を比較すると、「脳出血」の方が「脳梗塞」よりも高い傾向にあります。
これは、脳出血が脳組織を直接破壊したり圧迫したりする性質を持つためです。
どちらの病気がより重症であるかは、発症した脳の部位や出血・梗塞の範囲、治療開始までの時間、さらには患者さんの年齢や持病の有無によって大きく左右されます。
国立循環器病研究センターの研究によると、2010年から2016年の期間に入院した患者の入院後30日以内の死亡率は次のとおりです。
| 疾患名 | 入院後30日以内の死亡率 |
|---|---|
| 虚血性脳卒中(脳梗塞) | 4.4% |
| 脳内出血 | 16.0% |
| くも膜下出血 | 26.6% |
以上のデータからも、急性期における脳出血の危険性が伺えます。
脳出血や脳梗塞を発症したらすぐに救急車を呼ぶなどして、早急に医療機関を受診しましょう。
参考:脳卒中の予後(死亡率)と脳卒中専門医師数の関係について -ビックデータを用いて初めて可視化に成功―|国立循環器病研究センター
脳出血・脳梗塞後に残る後遺症と生活への影響
脳出血・脳梗塞の後遺症は、人によってさまざまですが、以下のような症状が長期間続くことがあります。
- 片麻痺(体の半分が動かしにくい)
- 言語障害(うまく話せない、言葉が出ない)
- 嚥下障害(食べ物や飲み物が飲み込みにくい)
- 認知機能の低下(記憶障害、判断力の低下) など
こうした後遺症によって、仕事ができなくなる、介護が必要になる、日常生活が自立できなくなるなど、人生に大きな影響が出ることもあります。
脳出血・脳梗塞の主な後遺症と生活への影響を下表にまとめました。
【脳出血・脳梗塞の主な後遺症と生活への影響】
| 後遺症の種類 | 具体的な症状 | 生活への影響 |
|---|---|---|
| 運動障害 | ・片麻痺(体の片側の麻痺) ・不随意運動(意思とは関係なく体が動く) ・運動失調(体の動きがふらつくなど、スムーズにできない)など | ・日常生活動作(ADL)の低下(着替え、食事、入浴、トイレなど基本的な生活動作の自立が困難になる) ・社会復帰や就労の制限 |
| 感覚障害 | ・しびれ ・痛み ・触れている感覚がわからないなど 麻痺と同じ側に生じることが多い | ・日常生活動作(ADL)の低下 ・QOL(生活の質)の低下 |
| 言語障害 | ・失語症(言葉を話す、理解する、読む、書くといった言語機能の障害) ・構音障害(発音の障害) | ・コミュニケーションの困難(家族や周囲との意思疎通が難しくなる) ・社会復帰や就労の制限 ・精神的ストレス。 |
| 高次脳機能障害 | ・記憶障害 ・注意障害 ・道具の使い方や着替えができない ・物や人が認識できない ・片側の空間が認識できないなど 認知機能に影響が出る | ・日常生活動作(ADL)の低下 ・コミュニケーションの困難 ・社会復帰や就労の制限 ・精神的ストレス ・家族への負担 |
| 視覚障害 | ・視野が狭くなる ・半分しか見えない ・物が二重に見える ・視力低下 など | ・日常生活動作(ADL)の低下 ・転倒リスクの増加 ・社会復帰や就労の制限 |
| 排泄障害 | ・頻尿 ・尿失禁 ・尿意がわからない ・尿が出ない など | ・日常生活動作(ADL)の低下 ・コミュニケーションの困難 ・社会復帰や就労の制限 ・精神的ストレス |
| 嚥下障害 | ・飲み込みがうまくできず、誤嚥性肺炎のリスクが高まる | ・栄養状態の悪化 ・誤嚥性肺炎による健康リスクの増加 ・食事の楽しみの減少 ・QOL(生活の質)の低下 |
| 感情障害 | ・気分の落ち込みやイライラ ・意欲低下など 感情が不安定になりやすく、うつ病を発症することもある | ・精神的ストレス(本人の精神的な苦痛) ・社会参加への意欲低下 ・家族への負担。 |
なお、脳梗塞や脳出血の後遺症の詳細は関連記事でわかりやすくご紹介しています。
 脳梗塞の後遺症とは?言語障害やしびれが出る?症状や仕事復帰を解説
脳梗塞の後遺症とは?言語障害やしびれが出る?症状や仕事復帰を解説
 脳出血の後遺症一覧!家族ができることや障害年金についてご紹介
脳出血の後遺症一覧!家族ができることや障害年金についてご紹介
脳出血・脳梗塞は障害年金の対象になる?
脳出血や脳梗塞によって後遺症が残った場合も、障害年金の支給対象となります。
障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出たときに申請できる公的な年金です。
障害年金を受給できるのは、次の3つの受給条件をすべて満たす人です。
- 初診日が国民年金または厚生年金の加入中であること
- 保険料を一定期間納付していること
- 障害の程度が国の定める基準に該当していること
障害年金の受給条件の詳細や、脳出血・脳梗塞での障害年金受給については関連記事をご覧ください。
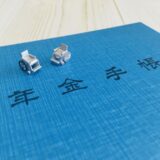 障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者
障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者
 脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
脳梗塞・脳出血で障害年金を受給するためのポイントと障害認定基準
障害年金を申請するには?社労士がサポートできること
障害年金の申請が難しいと感じるときは、障害年金専門の社労士に申請代行を依頼できます。
社労士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 年金事務所とのやり取り
- 医師への診断書作成依頼のアドバイス
- 病歴・就労状況等申立書など申請書類の作成 など
脳出血や脳梗塞で後遺症がある場合は、以前の生活と大きく変化し、ご自身のみならずご家族にも負担がかかるケースが見られます。
脳出血や脳梗塞の後遺症で辛いときに、年金事務所に何度も通うのは大変な労力となります。
社労士に依頼し障害年金申請の手間を省くことは、大きな利点となるでしょう。
社労士へ依頼するメリットについては下記で詳しくご紹介しています。
 障害年金の申請代行を社労士に依頼する4つのメリット
障害年金の申請代行を社労士に依頼する4つのメリット
脳出血での受給事例
ピオニー社会保険労務士事務所にご依頼いただき、脳出血で障害年金が受給できた事例をご紹介します。
脳出血(左被殻出血)で障害厚生年金2級を受給
- ご相談者:50代女性
- 病名:脳出血(左被殻出血)
- 審査結果:障害厚生年金2級
【ご相談時の状況】
夕食後に自宅で突然倒れ、救急搬送され、脳出血と診断されました。
数日後に意識が戻ったときには、四肢全てが動かず、言葉を発することもできず、寝たきり状態でした。
リハビリを始めてからは徐々に左上下肢は動かせるようになり、会話もできるようになりましたが、右上下肢は全く自力では動かせない状態でした。
【申請までのサポート内容】
車いすから降りることはできず、右手は動かすどころか温度を感じる感覚すらないとのことで、肢体の障害の2級以上には確実に該当していると判断できました。
まずは転院する病院を探してもらい、主治医と信頼関係を築いてもらうことをお願いし、タイミングを見計らって障害年金の診断書作成を依頼しました。
主治医は協力的な方で、障害年金制度や障害認定基準などをご理解いただいたうえで診断書を作成してくださいました。
【審査結果】
初診日から6か月を障害認定日として症状固定が認められ、2級に認定されました。
傷病手当金の支給と重なる期間が出たため、併給調整により数か月分の傷病手当金は返還することとなりました。
なお、上記の受給事例に出てくる障害年金と傷病手当金の併給調整は、関連記事でわかりやすくご紹介しています。
 傷病手当金と障害年金は両方もらえる?併給調整の注意点なども解説
傷病手当金と障害年金は両方もらえる?併給調整の注意点なども解説
ピオニー社会保険労務士事務所では、このほかにも脳出血や脳梗塞で数多くのご依頼をいただいています。
詳しくは、受給事例をご覧ください。
まとめ
脳出血と脳梗塞の違いを一言でいうと、発症の原因が脳血管が破れるのか、詰まるのかという点です。
初期段階では、脳出血の方が重症化しやすいですが、脳梗塞でも発症したらすぐに医療機関を受診することでその後の後遺症を軽くできる可能性があります。
もし脳出血や脳梗塞で後遺症が残ったときには、障害年金を申請できる可能性があります。
障害年金の申請が難しいと感じるときや、申請に不安があるときは、ぜひピオニー社会保険労務士事務所へご相談ください。
経験豊富な社労士が、あなたやご家族の障害年金申請をサポートします。